カーボンニュートラルはおかしいと言われる6つの理由とは?矛盾点や将来に向けた対応策を解説
更新日: 2026/1/8投稿日: 2025/8/31
EV
「カーボンニュートラルって本当に効果があるの?」「日本だけが頑張っても意味がないのでは?」「結局、誰が得して誰が損するの?」
ニュースやSNSで「カーボンニュートラル」という言葉を目にする機会が増えましたが、その政策に対して違和感や疑問を感じている方は少なくありません。
実際、Yahoo!知恵袋やSNSでは「カーボンニュートラルは欺瞞では?」「日本だけやりすぎでは?」といった声が多数寄せられています。
また、専門家の間でも「生産ベースの計測方法」や「国際的な不公平性」について議論が続いています。
この記事ではカーボンニュートラルについて、以下の内容を詳しく解説します。
- カーボンニュートラルが「おかしい」と言われる7つの具体的理由とデータ
- 構造的問題を解決するための現実的な対応策
- 企業が今日から始められる段階的アプローチ
そもそもカーボンニュートラルとは?

「カーボンニュートラルはおかしい」という声の背景を理解するために、まずは基本的な概念を正確に把握しておきましょう。実は、多くの人が誤解している点があります。
カーボンニュートラルの意味と定義
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの「排出量」から「吸収量・除去量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにした状態を指します。
ここで重要なポイントは、「CO2排出量を完全にゼロにする」のではなく、排出した分と同じ量を吸収・除去することで「差し引きゼロ(ネットゼロ)」にするという考え方です。
つまり、化石燃料の使用を完全に禁止するのではなく、排出した分を相殺すれば良いという仕組みです。この「実質ゼロ」という曖昧な概念が、後述する様々な矛盾や疑問の原因となっています。
「脱炭素」「ゼロエミッション」といったキーワードから「CO2を一切出さない」というイメージを持つ方も多いですが、実際にはそうではありません。
この認識のズレが「おかしい」という声につながっている側面もあるのです。
主な温室効果ガス一覧
カーボンニュートラルの対象となる温室効果ガスは、二酸化炭素だけではありません。以下の表で、主要な温室効果ガスとその特徴をまとめました。
| 温室効果ガス | 主な排出源 | 地球温暖化係数(CO2比) |
|---|---|---|
| 二酸化炭素(CO2) | 化石燃料燃焼、森林伐採 | 1 |
| メタン(CH4) | 畜産業、稲作、化石燃料採掘 | 28 |
| 一酸化二窒素(N2O) | 農業(肥料)、工業プロセス | 265 |
| フロン類(HFCs等) | 冷媒、発泡剤 | 1,300~23,000 |
| 六フッ化硫黄(SF6) | 電気機器の絶縁体 | 23,500 |
| 三フッ化窒素(NF3) | 半導体製造 | 16,100 |
日本の温室効果ガス総排出量のうち、二酸化炭素が約91.5%を占めているため、カーボンニュートラル達成には「排出抑制」と「吸収・除去」の2つのアプローチを組み合わせる必要があります。
カーボンニュートラルは誰が言い出した?
「カーボンニュートラルは上から押し付けられている」という印象を持つ方も多いでしょう。その背景には、この概念の歴史的経緯があります。
カーボンニュートラルという概念は、2007年4月にノルウェーのイェンス・ストルテンベルク首相(当時)が、2050年までに国家レベルで実現すると宣言したのが始まりとされています。
日本では2020年10月26日、菅義偉首相(当時)が臨時国会の所信表明演説で「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。
これにより、日本は2050年までに温室効果ガス排出を全体としてゼロにするという目標を国際社会に約束したのです。
つまり、カーボンニュートラルはわずか18年前に生まれた比較的新しい概念であり、急速に世界中に広まったことが「突然降って湧いた政策」という印象を与える一因となっています。
ただし、温室効果ガス削減の議論自体は1997年の「京都議定書」まで遡ることができ、国際社会では約30年にわたって議論が続いてきた経緯があります。
カーボンニュートラルが「おかしい」と言われる7つの理由

「カーボンニュートラルはおかしい」「欺瞞では?」という声が上がる背景には、感情論ではなく、具体的なデータに基づく構造的な問題があります。
ここでは、専門家や経済学者が指摘する主要な問題を7つに整理して解説します。
1.目標達成が現実的に困難である
日本政府は以下の目標を掲げています。
- 2030年:温室効果ガス排出量を2013年比で46%削減
- 2050年:カーボンニュートラル実現(実質ゼロ)
しかし、現実的な達成可能性には大きな疑問があります。最大の障壁は、日本のエネルギー供給構造です。
2022年度のエネルギー自給率はわずか13.0%で、エネルギー供給の約70%を石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料に依存しています。
| エネルギー源 | 構成比(2022年度) |
|---|---|
| 石油 | 36.9% |
| 石炭 | 25.2% |
| 天然ガス | 21.8% |
| 再生可能エネルギー | 10.2% |
| 原子力 | 5.9% |
政府の計画では2030年に再エネ比率を36〜38%まで引き上げる必要がありますが、現状の10.2%から残り約5年で3倍以上に増やす必要があり、達成は極めて困難と言わざるを得ません。
日本財団が実施した18歳意識調査でも、若者の多くが「2050年カーボンニュートラルは実現不可能」と認識しているというデータがあり、目標の現実性に対する疑問は広く共有されています。
2.主要排出国の取り組み次第で効果が限定的
「日本だけが頑張っても意味がないのでは?」という声は、データで見ると的を射た指摘です。2020年の世界の温室効果ガス排出量の内訳を見てみましょう。
| 国・地域 | 排出量(億トンCO2換算) | 世界シェア |
|---|---|---|
| 中国 | 140.9 | 30.7% |
| アメリカ | 62.5 | 13.6% |
| インド | 35.3 | 7.7% |
| ロシア | 21.7 | 4.7% |
| 日本 | 13.2 | 2.9% |
参考:全国地球温暖化防止活動推進センター「世界の二酸化炭素排出量(2020年)」
仮に日本が完全にカーボンニュートラルを達成しても、世界全体への影響はわずか2.9%にすぎません。中国とアメリカだけで世界の排出量の44.3%を占めています。
さらに問題なのは、中国は2060年、インドは2070年をカーボンニュートラル目標年としており、日本(2050年)よりも10〜20年遅い設定になっている点です。
「日本だけが経済的負担を負って努力する意味があるのか」という疑問が生まれるのは、このデータを見れば当然の帰結と言えるでしょう。
3.「生産ベース」計測による構造的不公平
カーボンニュートラルの「おかしさ」を象徴するのが、現在の計測方法に内在する重大な構造的問題です。
温室効果ガス排出量を「生産ベース」で計測する現行方式では、製品を製造した国でCO2排出量がカウントされます。この方法には以下の抜け穴があります。
- 先進国企業が発展途上国に工場を設立した場合、その工場からの排出は途上国側でカウント
- 先進国は自国の排出量を見かけ上削減できるが、地球全体の排出量は変わらない
- 途上国は「自国の消費実態を超えるCO2排出量の削減対策」を求められる
これは「カーボンリーケージ(炭素漏出)」と呼ばれる現象で、実質的に排出量の「輸出」が行われています。OECDの報告によると、日本は「消費ベース」で見ると排出量が増加する国のひとつです。
グローバルバリューチェーンが広がる中、この問題はますます深刻化しています。
4.年間90兆円規模の莫大なコスト負担
カーボンニュートラル達成のためにかかるコストは、想像を絶する規模です。経済産業省の試算によると、2050年カーボンニュートラル達成には累計約150兆円の追加投資が必要とされています。
また、複数の研究機関の試算では、日本がカーボンニュートラルを達成するためのコストは年間約90兆円とも言われています。
2024年度の日本の一般会計予算が約114兆円であることを考えると、国家予算の約80%に相当する巨額です。
さらに、国立環境研究所が2023年に発表した研究では、気候変動緩和策を実施した場合、2030年に約6,500万人、2050年に約1,800万人の貧困人口が増加する可能性があると指摘されています。
脱炭素化のための設備投資や炭素税による価格上昇が、特に途上国の低所得層に大きな負担を強いるためです。
このように、カーボンニュートラルは「気候変動対策」と「貧困問題」という2つの社会課題がトレードオフの関係に陥るリスクをはらんでいます。
5.再エネ導入が新たな環境破壊を引き起こす矛盾
「環境を守るため」とされる再生可能エネルギーの導入が、別の環境破壊を引き起こしているという皮肉な現実があります。
- 森林伐採とメガソーラー
大規模太陽光発電(メガソーラー)設置のために森林が伐採されるケースが全国で問題になっています。日本国内の太陽光発電設備の総面積は約6万ヘクタールに達し、東京ドーム約1万3千個分に相当します。森林伐採はCO2吸収源の減少だけでなく、土砂災害リスクの増加、生態系の破壊など、深刻な問題を引き起こしています。 - 風力発電と野生動物への影響
風力発電施設による「バードストライク」(鳥類の衝突死)は、アメリカだけで年間約10万〜44万羽と推定されています。また、低周波騒音による住民への健康被害や景観破壊も指摘されています。 - 太陽光パネルの廃棄問題
資源エネルギー庁の推計では、2040年には使用済み太陽光パネルが年間約80万トン発生すると予測されています。パネルには鉛やカドミウムなどの有害物質が含まれており、適切な処理が行われなければ新たな環境汚染につながります。
2021年に成立した改正地球温暖化対策推進法では、「ゾーニング」(地域特性を考慮した再エネ設置場所の適正化)が自治体の努力義務として定められましたが、実効性には課題が残っています。
6.特定業界への集中的な負担と経済的不公平
カーボンニュートラル政策は、すべての業界に等しく影響するわけではありません。この不公平さも「おかしい」と言われる大きな理由です。
負担が大きい業界:
- 製造業:生産過程でCO2を大量排出、設備更新に莫大な投資が必要
- 自動車業界:EV化への移行圧力、既存技術・雇用への影響
- エネルギー産業:石油・ガス精製の排出削減に大規模な技術革新が必要
- 鉄鋼・セメント業界:製造プロセス自体がCO2を排出、代替技術が限定的
負担が軽い業界:
- IT・サービス業:もともと排出量が少なく、再エネ電力への切り替えで対応可能
- 金融業:ESG投資で「環境配慮企業」としてアピールしやすい
日本では経済産業省が「排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業」を展開していますが、負担の格差を完全に解消するには至っていません。
7.対象範囲や検証基準が不明確
カーボンニュートラルには、実は明確な対象範囲や検証基準が定まっていないという根本的な問題があります。
- 地球全体で達成すべきなのか、国単位なのか、企業単位なのか
- 何をもって「達成」と認定するのか、誰が検証するのか
- カーボンオフセット(排出権取引)はどこまで認められるのか
この曖昧さゆえに、「カーボンニュートラル達成」を宣言する企業や国が現れても、その信憑性を客観的に検証することが難しいのが実情です。
基準が不明確なまま各企業が独自の定義で「達成」を主張すれば、グリーンウォッシュ(環境配慮の見せかけ)につながるリスクもあります。
カーボンニュートラルのおかしい点を解消できる対応策とは

ここまでカーボンニュートラルの問題点を指摘してきましたが、これらの課題には解決策も存在します。国際社会や専門家の間で議論されている改善策を紹介します。
排出量を「消費ベース」で測定する
「生産ベース」から「消費ベース」への計測方法の転換は、最も根本的な解決策のひとつです。消費ベースでは、製品が最終的に消費される国で排出量をカウントします。
- 先進国の「見かけ上の排出削減」を防止
- 輸入品に含まれるCO2排出量も自国の責任として認識
- 途上国への不公平な負担を軽減
- どこで温室効果ガスが排出されているかの実態が明確になる
EUでは既に「炭素国境調整メカニズム(CBAM)」の導入が進んでおり、輸入品に対して炭素価格を課す仕組みが整備されつつあります。
革新的技術の開発と実装加速
カーボンニュートラル実現には技術革新が不可欠ですが、「技術革新待ち」の姿勢には大きなリスクがあることも認識すべきです。
新技術の商業化には開発から普及まで長い時間がかかり、予想外のコスト増加や技術的課題が発生することも珍しくありません。技術革新に過度に依存すると、目標達成が大幅に遅れる可能性があります。
重要なのは、「将来の技術革新を待つ」のではなく、「今ある技術でできることから始める」という姿勢です。
技術革新が実現するまで何もしない「ゼロ」の状態でとどまるのではなく、既存技術で対応可能な「1」の取り組みを着実に進めておくことが重要です。
ライフサイクル全体でのCO2評価(LCA)の導入
製品の環境負荷を正確に評価するためには、「使用時」だけでなく、原材料調達から製造、使用、廃棄までの全過程で排出されるCO2を総合的に評価するLCA(ライフサイクルアセスメント)が不可欠です。
自動車業界を例に取ると、EVは走行時のCO2排出がゼロですが、バッテリー製造には大量のエネルギーを消費。
日本自動車工業会のデータによると、再生可能エネルギー供給が少ない日本では、LCAで見るとHV(ハイブリッド車)・EV・FCV(燃料電池車)のCO2排出量はほぼ同等になるケースもあります。
LCAの導入により、「EV=環境に良い」という単純な図式ではなく、各国のエネルギー事情に応じた最適な選択が可能になります。
カーボンニュートラルで期待される革新的新技術

カーボンニュートラル実現に向けて、様々な革新的技術の開発が進んでいます。これらの技術が実用化されれば、現在の問題点を解消できる可能性があります。
メタネーション技術:CO2を燃料に変える
メタネーションは、CO2と水素を反応させてメタン(合成天然ガス)を生成する技術です。サバティエ反応(CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O)を利用し、CO2を燃料として再利用することで、大気中のCO2を実質的に削減します。
既存の都市ガスインフラをそのまま活用できるため、新たなインフラ投資を抑えられる点が大きなメリットです。日本政府は2030年までに天然ガス供給量の1%(約90万トン/年)を合成メタンで賄うことを目標としています。
CCUS技術:CO2を回収・貯蔵・利用する
CCUSは「Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage」の略で、CO2を回収して貯蔵または利用する技術です。
- Capture(回収):工場や発電所から排出されるCO2を分離・回収(回収率約90%以上)
- Utilization(利用):回収したCO2を化学品・燃料・建材等の原料として活用
- Storage(貯蔵):地下1,000m以上の地層にCO2を圧入・貯留
日本では北海道苫小牧で実証プロジェクトが進行中で、累計30万トン以上のCO2貯留に成功しています。経済産業省は2050年に年間1.2億~2.4億トンのCO2貯留を目標としています。
ただし、大規模な地中貯留については、地震誘発のリスクを指摘する声もあり、慎重な検討が必要です。
カーボンリサイクル技術:CO2を資源化する
カーボンリサイクル技術は、CO2を「廃棄物」ではなく「資源」として活用する発想の転換です。
| 活用分野 | 具体例 |
|---|---|
| 化学品 | メタノール、ポリカーボネート、ウレタン |
| 燃料 | 合成燃料(e-fuel)、ジェット燃料 |
| 建材 | CO2吸収コンクリート |
| 藻類培養 | バイオ燃料、食品・飼料 |
特に自動車業界では、合成燃料(e-fuel)の開発が進んでおり、既存のエンジン技術を活かしながら脱炭素を実現できる選択肢として注目されています。
日本政府は2030年までにカーボンリサイクル関連市場を約1兆円規模に成長させることをが目標です。
企業がカーボンニュートラルに取り組むべき理由

これまでカーボンニュートラルの問題点を指摘してきましたが、「だから取り組まなくていい」という結論にはなりません。むしろ、問題点を理解した上で、適切な方法で取り組むことが企業にとって重要です。
異常気象リスクと企業への影響
世界気象機関(WMO)は、今後5年間で世界の気温が記録を塗り替える危険があると警告しています。温室効果ガスの増加とエルニーニョ現象の影響が重なり、地球規模の異常気象が発生する可能性が高まっているからです。
異常気象は、サプライチェーンの寸断、原材料価格の高騰、事業拠点への物理的被害など、企業経営に直接的な影響を与えます。
カーボンニュートラルへの取り組みは、単なる社会貢献ではなく、企業のリスク管理としても重要な意味を持つのです。
ESG投資と企業価値の関係
世界的にESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)が拡大しており、カーボンニュートラルへの取り組みは企業評価の重要な指標となっています。
- 世界のESG投資額:約35兆ドル(2020年)→約45兆ドル(2023年予測)
- 日本のESG投資額:約336兆円(2020年)→約500兆円超(2023年予測)
カーボンニュートラルに積極的に取り組む企業は、投資家からの評価が高まり、資金調達が有利になります。逆に、環境対策が遅れている企業は、投資対象から除外される「ダイベストメント」のリスクに直面します。
サプライチェーンからの要求
グローバル企業を中心に、サプライチェーン全体でのCO2削減を求める動きが加速しています。世界的にも、企業単体ではなくサプライチェーン全体での脱炭素化が主流です。
大手企業は取引先に対して、以下のような要求を行うケースが増えています。
- 自社のCO2排出量の開示(Scope1・2・3)
- 削減目標の設定と進捗報告
- 第三者機関による認証取得
- 再生可能エネルギーの使用比率向上
これらの要求に対応できない企業は、取引から除外されるリスクがあります。特に自動車業界や電機業界では、サプライヤーへの環境対応要求が厳しくなっており、中小企業にとっても対応が必須となっています。
Apple社は取引先に対して2030年までにサプライチェーン100%カーボンニュートラル達成を要請しており、日本企業も8社が対応を表明しています。
日本企業の取り組み状況と課題
日本企業の脱炭素経営への取り組み状況には、企業規模によって大きな差があります。
- 大企業:約7割が脱炭素経営に取り組んでいる
- 中小企業:取り組んでいるのは3割程度にとどまる
- ただし、中小企業の4割は「今後取り組む予定がある」と回答
中小企業の主な課題として、再エネ・新エネ導入における初期投資コスト、設備の設置場所の確保、専門知識やノウハウの不足が挙げられています。
現実的な対応策:段階的アプローチ
中小企業がカーボンニュートラルに取り組む際は、段階的なアプローチが重要です。いきなり完璧を目指すのではなく、できることから始めましょう。
ステップ1:現状把握(見える化)
- 自社のCO2排出量を算定(電気・ガス・燃料使用量から計算)
- 排出源の特定(どの工程・設備が多く排出しているか)
- ITシステムを活用した継続的なモニタリング体制の構築
ステップ2:省エネ・効率化(低コストで実施可能)
- LED照明への切り替え
- 空調設備の適切な温度管理
- 生産設備の効率化・更新
- 物流の最適化
ステップ3:再エネ導入(投資回収を見込める範囲で)
- 太陽光発電の設置(補助金活用)
- グリーン電力証書の購入
- 再エネ電力プランへの切り替え
ステップ4:サプライチェーン全体での取り組み
- 取引先との協力体制構築
- Scope3排出量の算定と削減
- カーボンオフセットの活用
特に重要なのがステップ1の「見える化」です。自社のCO2排出量を正確に把握しなければ、効果的な削減策を立てることはできません。
ITシステムを活用したCO2排出量の算定・管理は、カーボンニュートラル対応の第一歩です。
カーボンニュートラルはおかしい:まとめ

カーボンニュートラルの現行政策には、確実に解決すべき課題が存在します。
- 目標達成の困難さ:再エネ比率10%→36%を5年で実現する非現実性
- 国際的不公平性:日本の排出量は世界の2.9%、主要排出国との目標年のズレ
- 計測方法の問題:「生産ベース」による排出量輸出のカラクリ
- 莫大なコスト:年間90兆円規模の費用負担、途上国の貧困増加リスク
- 環境破壊の矛盾:再エネ導入による森林伐採・生態系破壊
- 業界間格差:特定産業への集中的な負担
- 基準の曖昧さ:対象範囲や検証基準が不明確
しかし、カーボンニュートラルへの取り組み自体を否定するのではなく、より効果的で公平な方法を模索することが大切です。
消費ベースでの排出量計測、LCA(ライフサイクルアセスメント)の導入、メタネーションやCCUSなどの革新的技術の開発により、現在の問題点は改善できる可能性があります。
企業にとっては、ESG投資やサプライチェーンからの要求に対応するため、カーボンニュートラルへの取り組みは避けて通れない課題です。
大企業の約7割が既に取り組んでいる中、中小企業も取り残されないための対応が求められています。
重要なのは、「技術革新を待つ」のではなく「今できることから始める」こと。問題点を理解した上で、段階的かつ現実的なアプローチで取り組むことが、企業の競争力維持につながります。
今後も当メディアでは、カーボンニュートラルに関する最新ニュースや、自動車業界における脱炭素の動向を発信していきます。
EVだけでなく、ハイブリッド車、水素、合成燃料など多様な選択肢について、データに基づいた情報をお届けしますので、ぜひ定期的にチェックしてみてください。
関連コラム

EV
【2025年版】EV(電気自動車)の補助金とは?申請の流れや注意点をわかりやすく解説
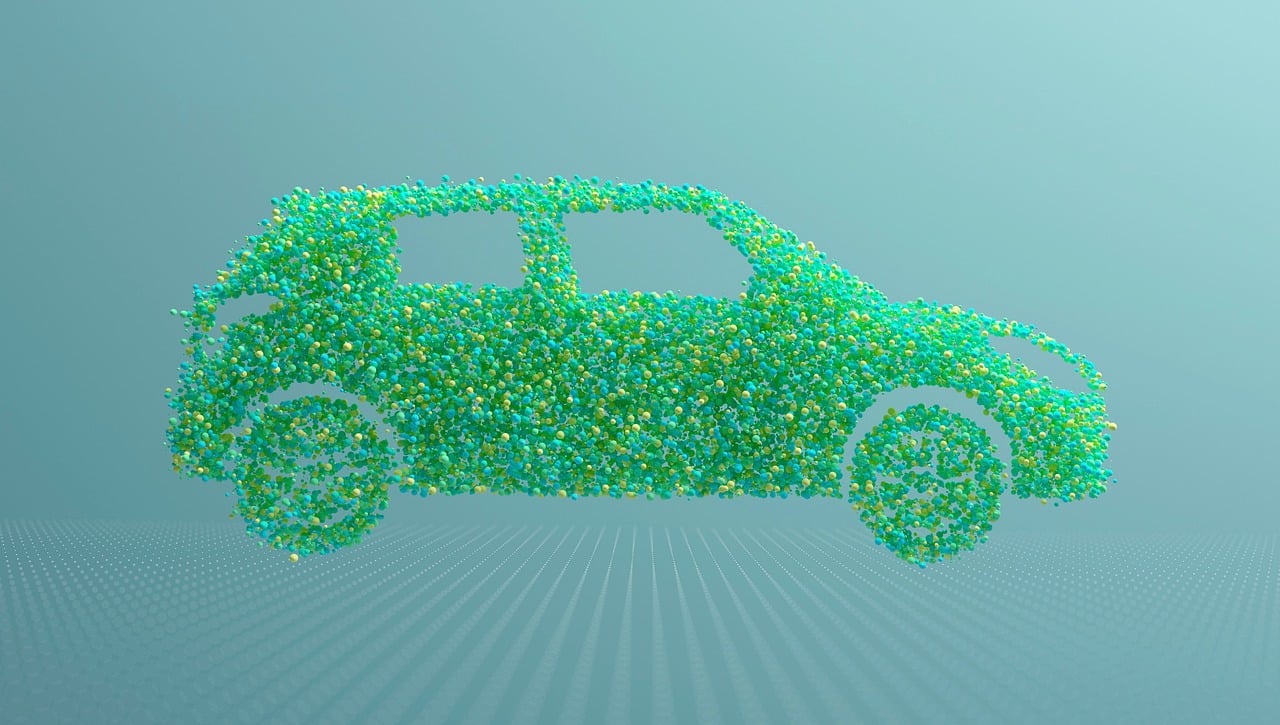
EV
【徹底解説】自動運転は本当に環境に優しい?知られざるメリット・デメリットと地球への影響

EV
EV充電スタンドはどこにある?種類や料金体系などを徹底解説

EV
【2025年版】電気自動車(EV)の充電料金は本当に安い?自宅や外出先の料金を徹底比較

EV
【なぜ?】EVが日本で「普及しない」本当の理由|デメリットから国の対策、今後の動向まで徹底解説

EV









