【徹底解説】自動運転は本当に環境に優しい?知られざるメリット・デメリットと地球への影響
更新日: 2026/1/6投稿日: 2025/7/3
EV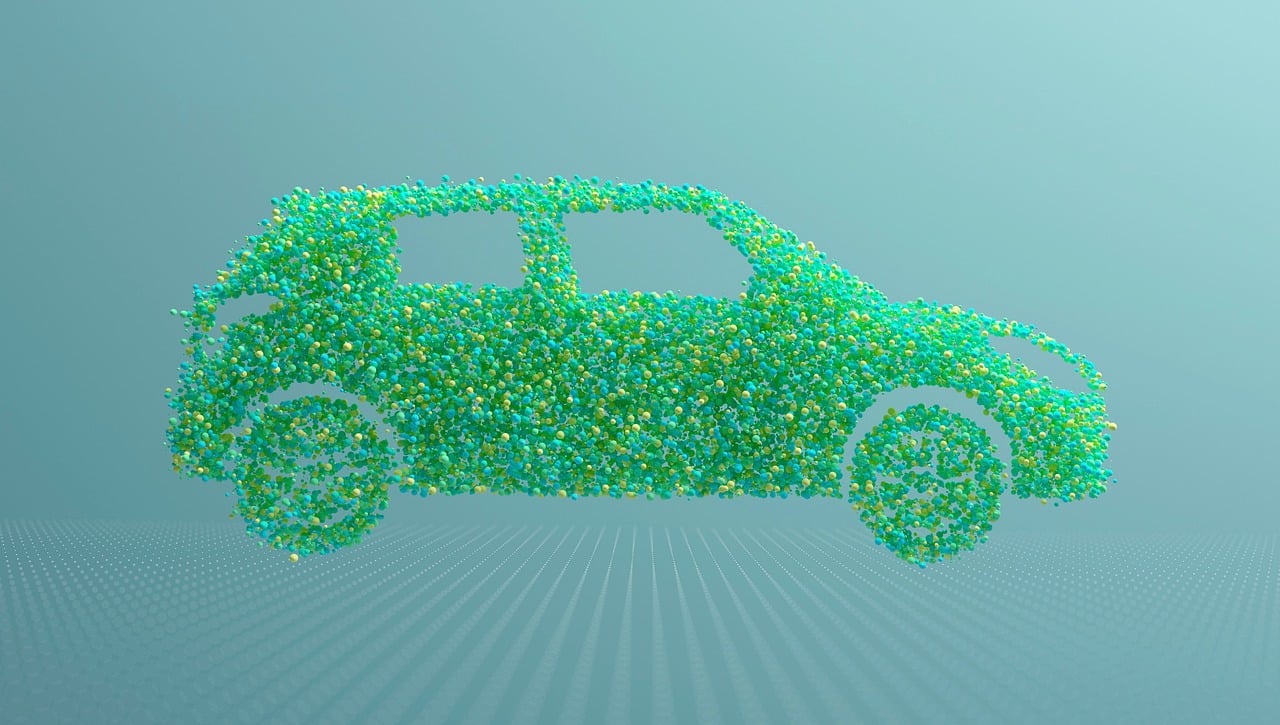
「自動運転って、無駄な加速・減速や渋滞がなくなるからエコロジーって聞くけど本当?」
「自動運転って、電気をたくさん使ったりするから地球の環境に悪いんじゃないの?」
どちらの考えも間違いではありません。自動車の自動運転が地球の環境に優しいのか、それとも環境に悪影響なのか、今の時点でははっきりとはわかっていないのが現状です。
本記事では、自動運転が環境に与えると予想されている影響を中心に、自動運転のメリットとデメリットを解説します。ぜひ、最後まで記事をご覧ください。
自動運転のレベルと現状

自動車の自動運転とは、自動車に搭載されたシステムやAI(人工知能)を利用してドライバーの運転を支援する、あるいはドライバーの代わりに運転を行う技術です。
自動車の自動運転には、レベル0~5までの段階があり、数字が大きいほど、システムによる運転操作への介入が大きくなります。自動運転レベルはアメリカの非営利団体「SAE International(自動車技術者協会)」によって定められており、その内容は以下の通りです。
| レベル | 概要 |
|---|---|
| 0 | 一切の自動化が行われていない状態 |
| 1 | アクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかが、部分的に自動化された状態。 |
| 2 | アクセル・ブレーキ操作およびハンドル操作の両方が、部分的に自動化された状態。 |
| 3 | 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。 ※ただし、自動運行装置の作動中、自動運行装置が正常に作動しないおそれがある場合においては、運転操作を促す警報が発せられるので、適切に応答しなければならない。 |
| 4 | 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。 |
| 5 | 自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。 |
現在日本国内で市販されている乗用車に搭載されている機能はレベル2までです。レベル2以下の自動運転は、ドライバーの運転操作の支援にとどまっています。厳密には自動運転車ではなく運転支援車です。
海外ではレベル3の乗用車も販売されていますが、実例は少ないです。
レベル4の自動運転車は、限られたエリアを走る自動車や、路線バスといった、限定的な環境での導入にとどまっています。また、国内の高速道路ではトラックのレベル4の自動運転を行うための実証実験が実施されています。
現状ではレベル4やレベル5の完全な自動運転が普及するまでの道のりは遠いと考えられますが、実現に向けて各国・企業が研究開発を重ねているのです。
日本の自動運転の進捗については、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひご確認ください。
自動運転の環境に対する影響

自動車の自動運転が地球の環境に与える影響には、ポジティブな影響もあれば、ネガティブな影響もあると予想されています。自動運転が実際に普及してみないと、どちらの影響がより大きくなるのかはわからないのが現状です。
ここではレベル4やレベル5の完全な自動運転が普及することによって想定される、環境に対するポジティブな影響(メリット)、ネガティブな影響(デメリット)の双方を解説します。
自動運転が環境に与えるポジティブな影響(メリット)

1.渋滞が緩和し、電力消費、騒音、振動などが減る
自動運転が普及すると、道路の渋滞が緩和されて、自動車の走行で消費されるエネルギーが減少すると考えられています。
自動運転車は、混雑している道路を回避するようなルート選択を行うと想定されています。また、渋滞を引き起こす原因になるような割り込みや急減速などは行わないでしょう。
現在の高速道路では、サグ部(下り坂から上り坂に変わる場所など)やトンネルの入口で、無意識のうちに自動車が減速して渋滞が発生しています。しかし、自動運転ならば無意識の減速による渋滞も防げます。
自動運転レベルが上がると、自分で運転する必要がないので、道路が混雑しない深夜時間帯に寝ながら移動するといったことも可能です。
渋滞が緩和されると、自動車が加速・減速を行う回数が減少するので、自動車が消費するエネルギー量が減少すると考えられます。騒音や振動といった周辺環境への悪影響も低減されるでしょう。
2.トラックが隊列走行を行い、空気抵抗が減少してエネルギー消費量が減る
物流トラックの自動運転が実現すると、複数台のトラックが短い車間距離で隊列走行を行うと考えられています。
隊列走行を行うと、列の後方を走るトラックが受ける空気抵抗が減少するので、走行に伴うエネルギー消費量が削減されます。
これはスリップストリームと呼ばれ、F1レースなどでもよく見られる光景です。
3.ドライバー不足が解消されて環境負荷の緩和に貢献できる
バスなどの公共交通機関のドライバー不足が解消されて事業の継続が可能となり、環境負荷の緩和に貢献できると考えられます。
近年は、バス事業者のドライバー不足が深刻な問題となっています。自動運転が普及すれば、将来的にはドライバーが不要となり、人手不足の解消に大きく貢献するでしょう。
ドライバーが不要になれば人件費の削減にもつながり、運賃の低廉化や、運行便数の増加といったメリットを、利用者にもたらすことが可能です。
バスが今後も持続可能な交通機関となり、盛んに利用されれば、環境面でのメリットは大きいと考えられます。マイカーを利用した場合と比べて、バスは乗客1人あたりのエネルギー消費量が少ない点が大きなメリットです。道路を走る自動車の削減につながるので、渋滞の緩和にも効果を発揮するでしょう。
4.ライドシェアが増加して車の走行距離が減る
自動運転の普及に伴い、ライドシェアの利用が増加して、自動車の総走行距離が減ると考えられます。
完全な自動運転車は無人状態でも走行できるので、ライドシェアの利用希望者のもとへ、手間をかけずに自動車を移動させることが可能です。また、人間のドライバーが不足しがちな深夜時間帯でも利用できます。ライドシェアの利用が現在よりも活発になると予想されます。
また、自動車を使って人の送迎を行うと、一般的には自動車やドライバーが元の場所へ戻るためだけに走行する、回送のような状態が発生します。しかしライドシェアならば、戻るときも移動したい人を乗せることが可能です。
ライドシェアの利用が増加することで、回送状態で走行する自動車が減れば、自動車の総走行距離も減り、エネルギー消費量の削減や渋滞の緩和につながります。
5.自動運転車の普及によって環境に優しい電気自動車が増える
自動運転車は、環境に優しいとされる電気自動車(EV)になることが前提となっています。
自動運転は、エンジンで走る自動車では実現できないということはありません。しかし、自動運転システムを稼働するためには大容量のバッテリーを搭載する必要があります。
電気自動車は走行のために元から大容量のバッテリーを搭載していますが、エンジン自動車に大きなバッテリーをあえて搭載するのは非合理的です。
また、電気自動車を駆動するモーターは、コンピューターによる電子的な制御との相性がよいです。エンジン自動車よりも停止や発進の制御が細かくできるので、電気自動車は自動運転に適しているとされています。以上の理由で、自動運転車は電気自動車でもあると想定されているのです。
電気自動車は、酸性雨の原因となる二酸化硫黄や窒素酸化物、温室効果ガスである二酸化炭素などを直接排出することはありません。自動運転車の実現は、電気自動車の普及にもつながり、環境への負荷を緩和するでしょう。
6.自動運転の電気自動車が再生可能エネルギー普及の契機になる
自動運転の電気自動車が普及することによって、再生可能エネルギーの利用が活発になることが期待されます。
電気自動車は排気ガスこそ出さないものの、走行等に必要な電力を火力発電で賄うと、温室効果ガスが発生してしまいます。
しかし、太陽光や風力といった再生可能エネルギーで電力を賄えば、地球環境への影響の低減が可能です。電力を消費する電気自動車が普及することが、再生可能エネルギーの普及拡大の契機になっていくのではないかと考えられます。
例えば、近年は屋根に太陽光パネルを備えている住宅が珍しくはありません。太陽光パネルがあれば、太陽光由来の電力を用いた電気自動車への充電が自宅で行えます。電気自動車が普及すれば、電気自動車の充電のために太陽光パネルを設置するという流れが加速するのではないかと考えます。
自動運転が環境に与えるネガティブな影響(デメリット)

1.コンピューターや通信設備の大量電力消費
自動運転車のコンピューターや通信機器が、大量に電力を消費することが、自動運転の環境面でのデメリットです。
アメリカ国立科学財団(NSF)は、世界各地の10億台の自動運転車が、それぞれ消費電力840ワットのコンピューターを搭載して1日1時間走行した場合のエネルギー消費量を算出しました。
算出した結果、10億台の自動運転車によって、世界の温室効果ガス排出量の0.3%、アルゼンチン1国の年間生成量に匹敵する量の温室効果ガスが生成されると発表されています。(参照:アメリカ国立科学財団、自動運転車のコンピュータによる温室効果ガス大量排出を報告|環境展望台:国立環境研究所 環境情報メディア)
自動運転車は、情報通信も盛んに行います。通信設備やデータセンターが大量に電力を消費することも懸念事項です。
2.電気自動車のバッテリーに関する環境問題
自動運転車は電気自動車であることが前提となっていますが、電気自動車のバッテリーは環境に悪影響だと言われています。
電気自動車に搭載されるリチウムイオンバッテリーは、製造時に大量のエネルギーと、リチウムやコバルトといった希少資源を消費します。
また、製造に必要なエネルギーが大きいことから、電気自動車1台の製造には、ガソリン車の2倍のエネルギーが必要という研究があります。バッテリーに用いる希少資源の採掘には、エネルギーや大量の水が必要なため、生態系に与える悪影響も無視できません。
また、使用済みのリチウムイオンバッテリーを再利用する技術は現在確立されておらず、適切な処理がなされていない場合があります。バッテリーには有害物質が含まれており、土壌や水質に悪影響を及ぼす可能性があるので、不適切に廃棄されるといったことは避けなければなりません。
3.自動車が簡単に利用できるようになるので走行距離が増える
誰もが簡単に自動車を利用できるようになるので、自動車の走行距離が増えて、消費エネルギーの増加や、渋滞の悪化につながる可能性があります。
自動運転車は人間が自分で運転をする必要がないので、自分で自動車を運転できない人であっても気軽に利用できます。これまで自動車を利用していなかった層が利用するようになれば、自動車の総走行距離は現在よりも増加するでしょう。
また、従来は自動車を運転するだけだった時間が、運転をシステムに行わせることで、生産的な行動にあてられます。すると、土地が安い郊外に住んで、都心の職場へ自動車で長距離通勤するという選択を、あえてする人も出てくるでしょう。
自動車を利用する人が増え、公共交通機関の利用が減少すれば、エネルギー消費量の増加や渋滞の悪化につながると考えられます。
4.道路のインフラ整備に伴う環境負荷
自動運転を実現するための道路のインフラ整備に伴って、環境負荷が発生することも懸念事項です。
高度な自動運転の実現には、地上から自動車へ情報を送る装置など、様々なインフラを整備する必要があると考えられています。人間が自動車を運転していた時代には必要なかったインフラの整備や使用、維持管理のために、エネルギーや資源が消費されることは、地球環境にネガティブな影響を及ぼすでしょう。
5.過度に慎重な運転を行うことによるエネルギー消費量の増加
自動運転システムは、過度に慎重な運転を行うことで、エネルギー消費量を増加させるかもしれません。
完全な自動運転を目指した技術開発は日々続けられていますが、システムが人間と同じような判断力を得られるのかは未知の領域です。人間のドライバーならば到底危険だとは判断しないような状況を危険な状況と誤認して、無駄な停車を行ってしまうという可能性も考えられるでしょう。
無駄な停車と再発進は、エネルギー消費量を増加させて、道路の渋滞も招きます。
日本の道路は、住宅街などの幅が狭い道路や複雑な交差点が多いです。危険な状況だと誤認することによる無用な停車を招きやすい状況にあるといえます。
自動運転のメリット4選

環境へのポジティブな影響以外にも、自動運転には様々なメリットがあります。今回はその中から4つを解説します。
1.交通事故の減少
自動運転車は、不注意や交通違反などが原因の事故を起こさないと考えられるので、交通事故が大幅に減少し、移動の安全性が大きく向上することが期待できます。
交通事故の減少により、ドライバーが加入する形の自動車保険の保険料が安くなる、あるいは全く不要になるというメリットも考えられます。
2.運転負荷の減少
人間が運転する必要がなくなるので、運転という負担から解放され快適に移動できます。読書や仕事をしたりして、時間を有効活用できるのです。あるいは、移動時間を睡眠や休憩の時間にあてることも可能です。
3.運転できない人の移動手段になる
子どもや高齢者などの自分で自動車を運転できない人が、容易に自動車で移動できるようになります。
特に地方では、ドライバーの不足により、高齢者の移動手段が減っている点が社会問題として挙げられています。自動運転が実現すれば、どんな地域でもスムーズな移動が可能になるでしょう。
4.迅速な災害対応が可能
災害発生時に出動する緊急車両や復旧のための重機を無人運転で動かせれば、すばやく対応できるようになります。二次災害に巻き込まれる可能性がある危険な場所にも、無人運転ならば入っていけることもメリットです。
自動運転のデメリット3選

自動運転の環境面以外におけるデメリットについても、3点解説します。
1.システムトラブルやハッキングのリスク
自動運転車は高度なコンピューター制御を行うため、システムにトラブルがあれば事故につながる可能性があります。現に2025年4月に、大阪・関西万博会場で自動運転機能を持っているバスが壁への接触事故を起こしています。
システムのエラーと設定ミスによって、パーキングブレーキがきかなくなったことが事故の原因でした。
また、車外との通信を前提としたシステムなので、ハッキングされて自動車が異常動作を起こし事故につながる可能性があります。ハッキングによって個人情報を抜き取られることも懸念事項です。
2.コストが高い
自動運転車には様々なセンサーや高性能なコンピューターを搭載する必要があり、車両コストが高くなると考えられます。
また、高度な自動運転を実現するためには、新たな運行管理システムの導入が必要です。そのコストは、運行管理システムの利用料として支払うとか、車両価格に上乗せされるといった形で、自動運転車の利用者が負担することになると考えられます。
3.無人運転であることによるリスク
完全な自動運転車にはドライバーがいないので、ドライバーがいる場合には問題にもならなかったような思いがけないリスクに直面する可能性があります。
アメリカ合衆国では、無人運転タクシーの乗客を足止めしようと考えた人物が、タクシーの前に立ちふさがってタクシーを立ち往生させたという事例が実際に起きています。足止め程度ならば危険性は低いですが、無人運転であるのをいいことに自動運転車を対象とした犯罪行為が多発するかもしれません。
【まとめ】自動運転が環境問題の解決につながるかは未知数。今後の技術開発や再生可能エネルギーの普及状況に要注目

自動運転が地球環境に優しいのか、それとも悪いのかは、現状では断言できません。しかし、少なくとも自動運転車が電力を大量に消費することは避けられません。大量の電力を、いかにして再生可能エネルギーで賄うかが、自動運転車が環境に与える負荷を大きく左右すると考えられます。
環境に対するデメリットの問題を解決するために、今後どのような技術開発やエネルギー政策が行われていくかが重要になることでしょう。
今後も当メディアでは、自動運転やEVなどのモビリティなどに関するニュースをまとめて発信していきます。最新情報が気になる場合は、ぜひ定期的にチェックしてみてください。
関連コラム

EV
【2026年】日本や世界の電気自動車(EV)の普及率は?普及への取り組みや今後の課題にも言及

EV
テスラの自動運転機能の現状は?事故の事例も解説

EV
中国の自動運転の現状は?実証実験や実例、事故など気になるポイントを解説

EV
EV(電気自動車)軽トラの車種や選び方を一挙紹介!メーカーごとの今後の展開も解説

EV
プラグインハイブリッド(PHEV)とは?HV/EVとの違いを一覧比較!「充電しないとダメ?」の疑問からメリット・デメリット、おすすめ車種まで徹底解説

EV







