MaaS(マース)とは?詳しい定義やメリット・導入事例を徹底解説
更新日: 2025/3/26投稿日: 2025/3/26
EV
近年「MaaS(マース)」という言葉を、ニュースや新聞で見る機会が増えてきました。
Maasは民間人の移動に大きな関わりがある仕組みであり、自動車業界との関連性も高いものとなっています。
「MaaSの意味と、導入するメリットを知りたい!」という方へ向けて、この記事ではMaaSの詳しい内容について、以下の4項目で解説します。
- MaaSの詳しい定義
- MaaSのレベル別解説
- MaaSを導入するメリット
- MaaSの国内事例
MaaSが私たちの生活にどう関わっているかが分かる記事になっているので、ぜひ最後までお読みください。
MaaS(マース)とは?

まずMaaSについて、以下の3項目で詳しく解説します。
- MaaSの定義
- MaaSの地域類型別モデル
- MaaSの歴史
MaaS(マース)の定義
MaaSとは「Mobility as a Service」の略語です。
MaaSはあらゆる人の移動ニーズに合わせて、複数の交通手段を1つのデジタルプラットフォームで統合し、効率化を図るサービスを指します。
つまり利用者が移動方法を検索し、予約・決済するまでの一連の流れが、同一プラットフォーム上ですべて完結するのが「MaaS」です。
MaaSを構築することで、移動手段や観光客誘致に問題を抱える地域社会の、さまざまな問題を解決できるとされています。
MaaS(マース)の地域類型別モデル
MaaSは構築する地域の特性に応じて、以下の5つのモデルに分けられます。
| モデル | 地域特性 | 地域課題 | 導入目的 |
|---|---|---|---|
| 大都市型 | 人口:大 人口密度:高 交通体系:鉄道主体 | 移動ニーズの多様化への対応 訪日外国人増加への対策 日常的な渋滞や混雑対策 イベントや災害等に起因する突発的な混雑解消 | 万人が利用しやすい都市交通の実現 訪日外国人の移動円滑化 日常的な混雑の緩和 |
| 大都市近郊型 | 人口:大 人口密度:高 交通体系:鉄道/自動車 | ラストワンマイル交通手段の不足解消 イベントや天候等による局所的な混雑解消 | 駅を核とした利便性の高い生活圏の確立 特定条件下で発生する局所的混雑の緩和 |
| 観光地型 | 人口:- 人口密度:- 交通体系:- | 観光産業の活性化 訪日外国人急増への対策 既存公共交通の混雑対策 | 観光客の回遊性の向上 訪日外国人の観光体験の拡大・向上 |
| 地方都市型 | 人口:中 人口密度:中 交通体系:自動車主体 | 自家用車への依存脱却 公共交通の利便性・事業採算性の低下への対策や運転手不足の解消 高齢者の移動手段確保 | 自家用車に依存しない地域内移動の創出 高齢者の移動手段確保 |
| 地方郊外・過疎地型 | 人口:低 人口密度:低 交通体系:自動車主体 | 自家用車への依存脱却 地域交通の衰退や運転手不足の解消 交通空白地帯拡大への対策 高齢者の移動手段確保 | 自家用車に依存しない地域内移動の創出 交通空白地帯での移動手段確保 |
モデルによって課題や導入目的は変わるため、地域に合わせたアプローチが重要です。
MaaS(マース)の歴史
MaaSは、2016年にフィンランドの取り組みによって世界的に注目され始めました。
フィンランドのモビリティアプリ開発会社「MaaS Global」が、世界初のMaaSプラットフォーム「Whim(ウィム)」を開発したことが大きなきっかけです。

フィンランドがMaaSを積極導入した1番の理由は、フィンランド国民の自動車依存が背景にあります。
フィンランドには国産の自動車メーカーが存在しないため、自動車売買による国益はありません。それにも関わらず、地方では自動車移動が8割を占めています。
国内には輸入車しか走っていないため、国民が自動車に依存し続けると国益を損ないます。国民に公共交通を積極利用して欲しい政府が打ち出したのが、MaaSへの取り組みです。フィンランドの取り組みはMaaSの先駆者として、世界各国で注目されました。
なお、日本国内では2017年から取り組みが始まり、2019年には「日本版MaaS」の実証実験を各地で開始しました。
日本のMaaSは近年急速に発展しており、社会課題の解決策として大いに期待されています。
5段階のMaaS(マース)レベルをそれぞれ解説

MaaSは統合度や機能の違いにより、以下5段階のレベルに分類されます。
- レベル0:統合なし
- レベル1:情報の統合のみ
- レベル2:複数の交通手段の統合
- レベル3:交通サービスの定額制・パッケージ化
- レベル4:政策や都市計画への統合
レベル0:統合なし
レベル0は、公共交通や民間交通手段の統合がいっさいなされていない、通常の状態です。各交通手段が完全に独立しており、乗り継ぎルートや時刻表も別々に調べる必要がある段階を指します。
現代の日本では、GoogleMapsによって目的地までのルートが一気に調べられます。また、ジョルダンやNAVITIMEなどのナビアプリにより、合計運賃や時刻表も確認可能です。
スマホ普及率がほぼ100%の日本は、すでにレベル0は脱却したといえるでしょう。
レベル1:情報の統合のみ
レベル1は交通情報の統合により、1つのアプリやプラットフォームで、複数交通手段の経路検索や運賃表を確認可能な状態です。
レベル1で統合される情報には、以下のものが含まれます。
- 駅、バス停、空港などの位置情報
- 路線、便、時刻表、運賃などの静的データ
- 遅延、到着予測、車両位置、運行情報などの動的データ
現在ではスマホアプリを駆使することで、どこへ行くにも交通ルートや運賃をチェック可能です。そのため、日本の大部分はMaaSレベル1に該当します。
レベル2:複数の交通手段の統合
レベル2は、複数交通手段を利用するにあたって、1つのプラットフォーム上で予約や決済ができる状態です。単一プラットフォーム上で目的地までの合計運賃が支払えれば、このレベルを実現しています。
日本においては、都市部はSuicaやPASMOにより支払いを1つのICカードで完結させられるため、一部分ではレベル2が実現されていると言えるでしょう。
ただし、地方や山間部、北海道などを網羅的にカバーするには至っていないので、完全なレベル2を実現したとは言えません。
レベル3:交通サービスの定額制・パッケージ化
レベル2は、複数の交通機関の予約や支払いが、1つのパッケージとして提供されている状態です。
代表例が、フィンランドに存在した「Whim」です。月額制で鉄道やバス、タクシーが乗り放題のサブスクリプションサービスであり、レベル3に該当します。
交通機関のルート検索、予約、決済が一括でできるWhimは、移動のプラットフォームアプリ。(中略)特徴は、乗り放題のサブスクリプションサービス。月額でお金を支払えば対応するモビリティを自由に利用でき、わざわざ移動のたびにお金を支払う必要はない。
日本では、JR東日本が提供している「東京フリーきっぷ」のような1日乗車券が近いものと言えます。ですが、本格的なレベル3サービスは、まだ存在していません。
レベル4:政策や都市計画への統合
レベル4は、政策や都市計画レベルでレベル3を実現できている状態です。
交通サービスだけでなく、都市設計や政策立案において、自然にMaaSの概念が取り入れられていればレベル4にあたります。
現在、世界的にもレベル4を完全に実現できている国や地域はありません。
MaaS(マース)を導入する9つのメリット

MaaSを導入する多くのメリットから、代表的なものを9つ紹介します。
1. 都市交通の効率化
2. CO2排出削減による環境改善
3. 交通の地域格差の是正
4. 高齢者の移動の利便性向上
5. 観光地の振興
6. 公共交通機関の事業収益最大化
7. 災害時の円滑な対応
8. 物流の活性化
9. スマートシティ構想の実現
1. 都市交通の効率化
MaaSを導入すれば、利用者は単一プラットフォーム上で複数の交通手段を簡単に利用できます。
混雑状態や運行状況がリアルタイムで取得できるので、最適かつ効率的な移動ルートがすぐ選択可能です。
とくに都市部では交通網が複雑に入り組んでいるため、同一プラットフォーム上でルート確認と決済が同時にできれば、交通の流動性は大幅に改善するでしょう。
2. CO2排出削減による環境改善
MaaSの導入により公共交通やシェアカーを活用する社会になれば、必然的に自家用車の利用率は下がります。
ガソリン車の利用が減ってCO2排出量が下がれば、環境負荷の軽減が期待できます。ここに、現在世界的に普及が推進されるEVを組み込めれば、相乗効果でさらに環境改善が進むでしょう。
世界的な環境問題の改善という面から見ても、MaaSの推進は重要事項です。
3. 交通の地域格差の是正
地方や山間部など、交通の過疎地域では交通網の空白地帯が問題になっています。
ここにMaaSでオンデマンド交通や自動運転車タクシーを導入することで、交通の地域格差を是正可能です。
自動運転車がサービスカーとして導入され、交通データの活用により最適な公共交通バス運用の取り組みが進めば、交通手段が少ない地域に住む人々の大きな助けになります。
4. 高齢者の移動の利便性向上
高齢化が進む日本社会において、移動弱者が快適に移動できる環境を整えるのは、今後の重要な課題です。
誰でも使いやすいMaaSアプリを開発・普及できれば、高齢者でも公共交通やオンデマンド交通を簡単に利用できます。
さらに、現在研究されている自動運転タクシーが普及すれば、地方や山間部においても移動に困ることはほぼなくなるでしょう。
5. 観光地の振興
不慣れな土地を移動する必要がある観光客は、必然的に現地民より多くの時間を交通に費やします。
MaaSの導入によりスムーズな移動が実現すれば、旅行者はルートの確認や決済に時間を浪費することなく観光を楽しめます。
交通より観光に時間を使えるようになれば、観光収益の向上が見込めるでしょう。また、京都や沖縄などの混雑しがちな観光地のオーバーツーリズム解消にも一役買います。
6. 公共交通機関の事業収益最大化
MaaSにより市民が公共交通機関を使うようになれば、利用者増加により運賃収入の増加が見込めます。
また、MaaSの構築は利用者データの収集がしやすくなるため、運行ダイヤの適正な見直しを促進し、コスト削減が可能です。
とくに近年の地方では、人口減少や少子化で発生した不採算路線の見直しが課題です。MaaSで収集したデータを活用すれば、路線の最適化が可能になります。
7. 災害時の円滑な対応
地震や豪雨などの災害により主要交通手段が寸断された際でも、MaaS基盤を活用して利用可能な代替移動手段を確保・提示可能です。
また、災害時の交通機関やホテルのキャンセル情報を1つのプラットフォームで確認できれば、被災者を受け入れられる避難先との効率的なマッチングにつながります。
具体例として挙げられるのが、熊本県の赤十字病院です。熊本赤十字病院はトヨタ自動車九州の協力のもと、防災に関する実証実験を行っています。
また、避難先をどうするか、という点にも取り組んでいます。日本の避難所というのはなかなか過酷な環境ですから、あらかじめホテルなどの宿泊施設に避難したほうがはるかに快適に過ごせるはずです。そこで、災害が予想される状況になったら、安全な地域の宿泊施設とそこまでの経路・交通手段を表示し、それをまとめて一括予約できる仕組みを考えています。
熊本では、EVを非常用電源として避難所に送ることにより、電力不足を供給する協定もMaaSの一環として締結されています。
自然災害大国日本にとって、防災とMaaSをかけ合わせた取り組みは、今後ますます重要になるでしょう。
8. 物流の活性化
現在、物流業界は深刻な人手不足と2024年問題による残業規制で、大きな問題を抱えています。
MaaSを物流に応用できれば、物流事業者と交通事業者の連携により、配達ルートの最適化が可能です。
業務効率が向上すれば、ドライバー不足の問題を大きく緩和できます。
9. スマートシティ構想の実現
スマートシティとは、ICTやAIなどのデジタル技術を駆使し、人々の生活を快適かつ豊かにする都市のことです。
スマートシティとは、「都市内に張り巡らせたセンサー・カメラ、スマートフォン等を通じて環境データ、設備稼働データ・消費者属性・行動データ等の様々なデータを収集・統合してAIで分析し、更に必要に応じて設備・機器などを遠隔制御することで、都市インフラ・施設・運営業務の最適化、企業や生活者の利便性・快適性向上を目指すもの」です。
引用:スマートシティとは
MaaSにより現在の交通状況をデジタル技術で分析・活用できれば、スマートシティ構想の実現に大きく貢献します。逆に言えば、スマートシティの実現にはMaaSの導入は不可欠です。
MaaSの導入は単なる交通サービスの統合にとどまらず、社会全体の効率化や環境改善、地域活性化など、多岐にわたる効果をもたらします。
MaaS(マース)の国内事例を2つ紹介

ここからは、MaaSの実際の国内事例を2つ紹介します。
1. JR西日本のMaaSアプリ「tabiwa by WESTER(タビワ バイ ウェスター)」
2. トヨタ自動車とJR西日本のMaaSアプリ「my route(マイルート)」
1. JR西日本のMaaSアプリ「tabiwa by WESTER(タビワ バイ ウェスター)」

tabiwaの利用可能エリア
- 岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県および高知県を中心とするせとうちエリア
- 福井県・石川県・富山県・新潟県(一部)および長野県(一部)の北陸エリア
- 鳥取県・島根県(一部)の山陰エリア
「tabiwa by WESTER」は株式会社アイリッジが提供する観光型MaaSアプリです。旅の予約やチケットの利用をスマートフォンでキャッシュレス、チケットレスで行えます。
サービスの主な特徴は、以下のとおりです。
- おトクなチケットの購入
- おトクなJRセットプランや宿泊プランの検索
- 目的地までの経路検索
- 共有可能な旅のスケジュール作成
- 話題のスポットを写真や動画で紹介
- おすすめモデルコースの紹介
当該エリアへの旅行は、tabiwaをインストールするだけでOK。エリア内の特定交通機関が乗り放題の周遊パスも購入でき、都度決済の煩わしさから解放されます。
上記内容から、tabiwaはまさにMaaSのモデルケースと言えます。
2. トヨタ自動車とJR西日本のMaaSアプリ「my route(マイルート)」
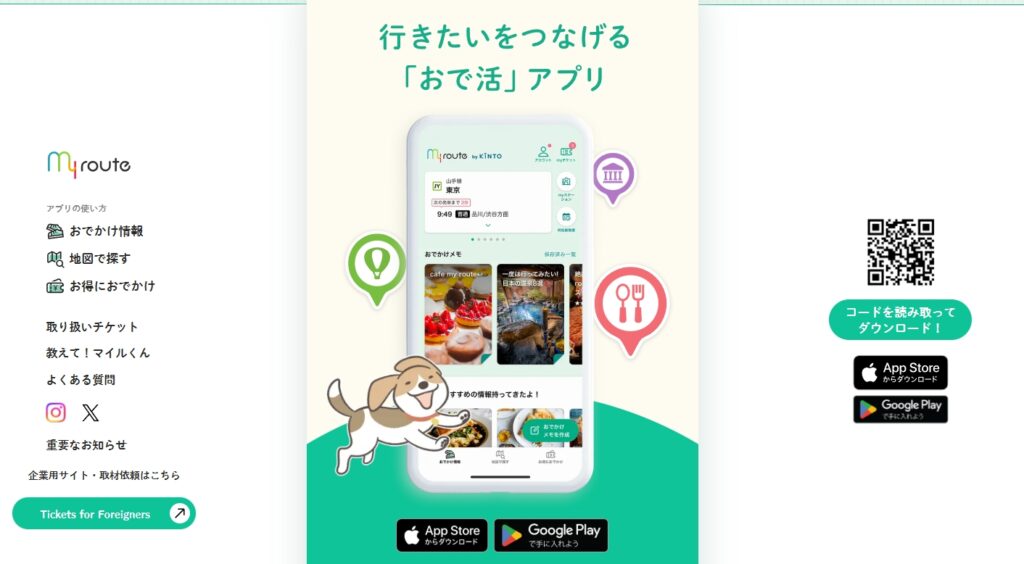
「my route」は、トヨタ自動車が提供する、国内最大級のMaaSアプリです。電車やバス、タクシーなど複数の移動手段を、1つのプラットフォームで検索・予約・決済できます。
一部の機能は全国で利用できますが、対応地域であればさらに便利。気になる店やスポットのお気に入り登録機能や、簡単に最寄り駅やバス停の発車時刻を確認できる機能が使えます。
現在、さまざまなエリアで実証実験を行っており、最終的には全国への普及を目指しています。
日本が抱えるMaaS(マース)導入のための課題

日本ではMaaSの導入が進みつつありますが、今後の普及にはさまざまな課題が山積みです。
MaaS普及の代表的な課題
- 自動運転車の導入にともなう法整備
- 地域間格差と普及のための戦略
- 利用者への認知
これらの課題を乗り越えるには、各公共交通機関や自動車メーカー、国土交通省が密な連携で進めていく必要があります。
【まとめ】MaaS(マース)導入は日本の重要な課題

MaaSは、交通に関する利便性を大きく高めるシステムとして、現在注目されています。
日本社会は少子高齢化や人材不足により、交通面で多くの問題を抱えています。MaaSの導入が進めば、それらの問題を一挙に解決する可能性を秘めているのです。
今後は交通事業者や行政、自動車メーカーが連携し、課題に沿ったMaaS構築を進めることが、日本における「持続可能な社会」を実現する鍵となるでしょう。
関連コラム
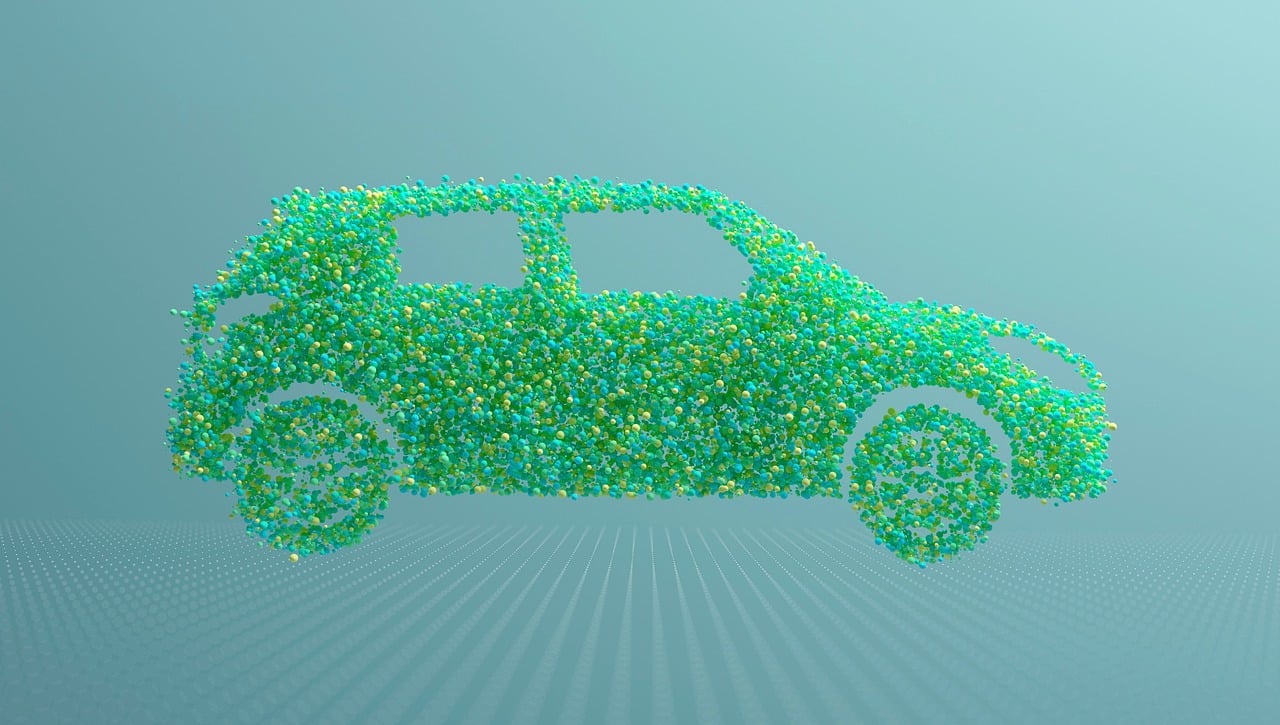
EV
【徹底解説】自動運転は本当に環境に優しい?知られざるメリット・デメリットと地球への影響

EV
【総まとめ】電気自動車(EV)のメリット7選!デメリットをカバーする方法も合わせて解説

EV
【完全解説】カーボンニュートラル燃料とは?基礎知識からメリット・デメリットまで徹底解説

EV
自動運転の開発が一番進んでるメーカーはどこ?国内と海外の自動運転関連企業を紹介

EV
【2025年版】電気自動車(EV)の充電料金は本当に安い?自宅や外出先の料金を徹底比較

EV









