水素自動車とは?仕組みやメリット・デメリットを徹底解説
更新日: 2026/1/6投稿日: 2025/9/25
EV
「水素自動車って本当に環境に良いの?」「EVとどう違うの?」「なぜまだ普及していないの?」
次世代のエコカーとして注目される水素自動車ですが、実際の仕組みやメリット・デメリット、そして現実的な導入可能性について、正確な情報を持っている方は少ないのではないでしょうか。
2025年現在、日本国内の水素ステーションはわずか約149箇所にとどまり、EVの充電スポット約21,000箇所と比較すると圧倒的に少ない状況です。
一方で、政府は2030年までに1,000箇所の設置を目標に掲げており、今後の急速な普及が期待されています。
この記事では、2025年最新のデータと世界の動向に基づき、水素自動車の技術的特徴から実用面での課題、購入時の補助金情報まで、徹底解説します。
水素自動車の導入や次世代エコカーの選び方でお悩みの方は、Carconnectの無料相談をご活用ください。専門スタッフが最適な選択をサポートいたします。
水素自動車とは?

水素自動車とは、水素をエネルギー源として走行する自動車の総称です。ガソリンや軽油ではなく、水素を燃料として動力を得る点が最大の特徴。
水素自動車は走行時に温室効果ガスを排出しない「ゼロエミッション車」の1つとして、カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要な選択肢として注目されています。
水素自動車には大きく分けて2つのタイプが存在し、それぞれ異なる仕組みで走行します。
水素エンジン車
水素エンジン車は、ガソリンの代わりに水素を内燃機関(エンジン)で直接燃焼させて動力を得る自動車です。
従来のガソリンエンジンの構造を大きく変更することなく、燃料を水素に置き換えることで実現できるため、既存のエンジン技術を活かせるというメリットがあります。
水素エンジン車の特徴は以下のとおりです。
- 内燃機関で水素を燃焼させる仕組み
- 排出されるのは水蒸気と微量の窒素酸化物のみ(CO₂排出なし)
- ガソリンエンジンからの改造が比較的容易
- トヨタが2021年からモータースポーツで開発を推進中
ただし、2025年11月現在、一般消費者向けに市販されている水素エンジン車はまだ存在しません。
トヨタ自動車が市販化を目指して研究開発を進めており、レース車両での実証データを蓄積しながら今後の展開を準備しています。
水素燃料電池自動車(FCV)
燃料電池自動車(FCV:Fuel Cell Vehicle)は、水素と酸素の化学反応で発電した電気を使ってモーターを駆動する自動車です。
車載された燃料電池スタック内で「水素+酸素→電気+水」という化学反応が起こり、その電気エネルギーでモーターを回して走行します。
2014年にトヨタが世界初の量産型FCV「MIRAI」を発売し、現在まで累計1万台以上を販売しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 動力源 | 水素と酸素の化学反応で発電 |
| 発電方法 | 燃料電池スタックで車内発電 |
| 排出物 | 水(H₂O)のみ |
| 補給場所 | 水素ステーション(全国約149箇所) |
| 充填時間 | 約3〜5分 |
| 代表車種 | トヨタ MIRAI、ホンダ CR-V e:FCEV |
FCVは走行中にCO₂を一切排出しないという点で、環境性能に非常に優れた「究極のエコカー」として位置づけられています。
電気自動車(EV)との違い
水素自動車(FCV)と電気自動車(EV)は、どちらも「モーターで走行する」という点では共通していますが、電気の供給方法が根本的に異なります。
| 比較項目 | FCV(水素自動車) | EV(電気自動車) |
|---|---|---|
| 電気の供給方法 | 車内で発電(燃料電池) | 外部から充電(バッテリー蓄電) |
| エネルギー源 | 水素 | 電力 |
| 補給時間 | 約3〜5分 | 30分〜数時間 |
| 航続距離 | 約650〜850km | 約300〜600km |
| インフラ数(2025年) | 約149箇所 | 約21,000箇所以上 |
| エネルギー効率 | 約30%程度 | 約80%弱 |
FCVは「車内で電気を作る」のに対し、EVは「電気を外部から受け取る」という点が最大の違いです。
FCVは燃料電池に発電機能があるため、EVよりも長い航続距離(約650〜850km)を実現できます。一方、EVは充電インフラが整備されている点で利便性に優れています。用途や生活環境に応じた選択が重要です。
水素自動車の4つのメリットを電気自動車やガソリン車と比較して解説

水素自動車(FCV)には、環境性能や実用性の面で注目すべき4つのメリットがあります。ここでは、EVやガソリン車と比較しながら詳しく解説します。
1. 環境に非常に優しい
水素自動車の最大のメリットは、走行中に排出されるのが「水(H₂O)」のみという点です。
| 車種タイプ | 走行中の排出物 | 環境負荷 |
|---|---|---|
| FCV(水素自動車) | 水のみ | ★★★★★ 極めて低い |
| EV(電気自動車) | 排出物なし | ★★★★☆ 低い |
| ガソリン車 | CO₂、NOx、PMなど | ★★☆☆☆ 高い |
環境面での具体的なメリットは以下のとおりです。
- CO₂排出ゼロ:走行時に二酸化炭素を一切排出しない
- 大気汚染物質ゼロ:窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)も排出しない
- カーボンニュートラル実現:2050年の脱炭素社会実現に貢献
- 再生可能エネルギー活用:グリーン水素を使用すれば製造過程も含めてクリーン
ただし、現在主流の「グレー水素(化石燃料由来)」では製造過程でCO₂が発生します。
日本政府は2030年までにグリーン水素とブルー水素を合わせたクリーン水素供給量を42万t以上にする目標を掲げており、製造から利用までのトータルで見た環境性能も今後改善が期待されます。
2. 長距離走行が可能
水素自動車は一度の水素充填で650km〜850kmの長距離走行が可能です。これはガソリン車と同等、EVを大きく上回る航続距離となります。
| 車種 | 航続距離(カタログ値) | タイプ |
|---|---|---|
| トヨタ MIRAI | 約850km | FCV |
| トヨタ クラウンセダンFCEV | 約820km | FCV |
| ホンダ CR-V e:FCEV | 約750km | FCV |
| 日産 アリア | 約610km | EV |
| テスラ モデル3 | 約580km | EV |
トヨタMIRAIは2021年にフランスで1回の充填で1,000km走行を達成した記録もあり、実用性の高さが証明されています。
長距離走行のメリットは以下のとおりです。
- 長距離ドライブや出張でも安心
- 営業車や配送車など業務用途に最適
- 「航続距離不安(レンジアンクシエティ)」が少ない
- 高速道路での長距離移動も余裕を持って対応可能
3. 充填スピードが速い
水素自動車の大きなアドバンテージが、水素充填時間が約3〜5分と非常に短い点です。これはガソリン車の給油とほぼ同じ感覚で利用できます。
| 車種タイプ | 補給・充電時間 | 利便性 |
|---|---|---|
| FCV(水素自動車) | 約3〜5分 | 非常に高い |
| ガソリン車 | 約3〜5分 | 非常に高い |
| EV(急速充電) | 約30分〜1時間 | やや低い |
| EV(普通充電) | 約8〜12時間 | 低い(夜間充電向け) |
充填スピードのメリットは以下のとおりです。
- 忙しいビジネスシーンでも時間を取られない
- 長距離移動時の休憩時間で補給完了
- タクシーや配送など稼働率が重要な業務用途に最適
- 従来のガソリン車と同じ感覚で使える
特に商用車や大型トラック、バスなどの分野では、充電時間の短さが大きな競争優位性となるため、水素自動車への期待が高まっています。
4. 静音性が高い
水素自動車はモーター駆動のため、エンジン車と比べて圧倒的に静かです。これはEVと同様のメリットとなります。静音性のメリットをまとめました。
- 快適な車内空間:エンジン音や振動がなく、会話や音楽を楽しめる
- 疲労軽減:長時間運転でも騒音ストレスが少ない
- 住宅地での配慮:早朝・深夜の出発でも近隣への騒音が少ない
- 高級車としての品質:静粛性は高級車の重要な要素
ただし、歩行者が車の接近に気づきにくいという側面もあるため、低速走行時には車両接近通報装置が作動する仕組みになっています。
水素自動車のデメリット
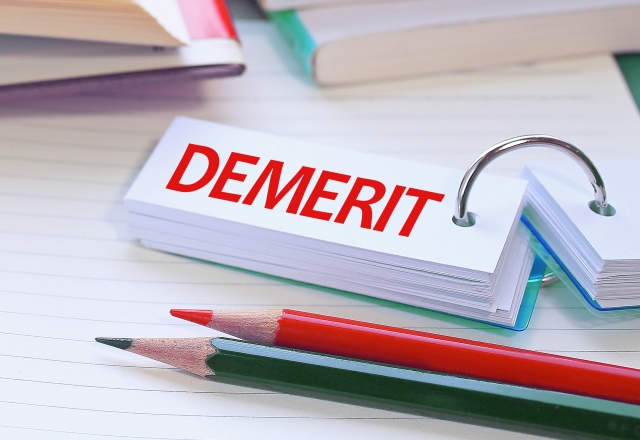
多くのメリットがある水素自動車ですが、実用面では解決すべき課題も存在します。ここでは、購入検討時に必ず確認すべき3つの主要なデメリットを解説します。
水素ステーションの数が少ない
水素自動車の普及における最大の障壁がインフラ不足です。2025年現在、全国の水素ステーション数はわずか約149箇所にとどまっています。
| 地域 | 水素ステーション数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 首都圏 | 約47箇所 | 東京・神奈川・埼玉・千葉 |
| 中京圏 | 約45箇所 | 愛知・岐阜・三重 |
| 関西圏 | 約18箇所 | 大阪・京都・兵庫 |
| 九州圏 | 約11箇所 | 福岡中心 |
| その他地域 | 約28箇所 | 北海道・東北・中国・四国など |
| 設置ゼロの県 | – | 長崎・宮崎・沖縄など |
EVの充電スポットは約21,000箇所以上、ガソリンスタンドは約28,000箇所という状況と比べると、水素ステーションのインフラ整備は圧倒的に遅れています。
インフラ不足による具体的な問題をまとめました。
- 地方での利用困難:県によっては1箇所もない地域がある
- 営業時間の制約:24時間営業の水素ステーションは限定的
- 移動ルートの制限:水素ステーションの場所を考慮した行動が必要
- 高速道路上の不在:2025年11月現在、高速道路SA/PAには設置がほぼない
政府は2030年までに1,000箇所の設置を目標に掲げ、2024年度には約100億円の予算を投入してインフラ整備を推進しています。今後の整備状況を注視することが重要です。
水素燃料が高い
水素の燃料価格は、1kgあたり約1,650円〜2,200円(2025年現在)と高額です。2024年4月以降、化石燃料価格の上昇や世界的なインフレの影響を受け、約36%値上げされています。
| 項目 | トヨタ MIRAI(例) |
|---|---|
| 水素タンク容量 | 約5.6kg |
| 満タン充填費用 | 約9,240円〜12,320円 |
| 航続距離(カタログ値) | 約850km |
| 燃費コスト | 約10.9円〜14.5円/km |
他の燃料との比較(参考)は以下のとおりです。
- ガソリン車:約8〜12円/km(燃費15km/L、ガソリン170円/Lと仮定)
- EV:約3〜5円/km(家庭充電の場合)
- FCV:約11〜15円/km
経済産業省は「2030年までに水素価格を334円/kg(30円/N㎥)まで引き下げる」目標を掲げています。この目標が達成されれば、燃費コストは現在の約5分の1まで改善される見込みです。
車体価格が高い
水素自動車(FCV)の車両価格は、一般的なガソリン車やEVと比べて非常に高額です。
| 車種 | メーカー希望小売価格 | CEV補助金適用後(目安) |
|---|---|---|
| トヨタ MIRAI(FCV) | 約741万円〜861万円 | 約486万円〜606万円 |
| トヨタ クラウンFCEV | 約830万円〜 | 約575万円〜 |
| ホンダ CR-V e:FCEV | 約809万円 | 約554万円 |
| トヨタ プリウス(HEV) | 約275万円〜 | – |
高額な理由は以下のとおりです。
- 燃料電池スタックのコスト:レアメタル(白金など)を使用した触媒が高価
- 高圧水素タンク:70MPaの超高圧に耐える特殊な材料と製造技術が必要
- 生産台数の少なさ:量産効果が得られず製造コストが高い
- 開発コストの回収:先進技術への投資コストが価格に反映
活用できる補助金制度は以下のとおりです。
- 国の補助金(CEV補助金):最大255万円
- 自治体の補助金:都道府県・市区町村で独自の補助制度あり(併用可能)
- 保有義務期間:4年間の保有が条件
補助金を最大限活用しても、FCVの実質負担額は500万円前後となります。購入前に必ず最新の補助金情報と自治体独自の支援制度を確認しましょう。
補助金が利用できる水素自動車(FCV)の車種一覧

2025年11月現在、日本国内で購入・リースできる主要なFCVは4車種です。ここでは、CEV補助金の対象となっている各車種の特徴とスペックを詳しく解説します。
トヨタ クラウン(CROWN)セダン FCEV

トヨタ クラウンセダンFCEVは、伝統的なクラウンブランドに最新の水素燃料電池技術を組み合わせた高級セダンです。2023年11月に発売され、ショーファーカー(運転手付き車両)としての性質を重視した設計が特徴です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| メーカー希望小売価格 | 約830万円〜 |
| 航続距離 | 約820km(WLTCモード) |
| 水素充填時間 | 約3分 |
| 特徴 | ・ホイールベースを80mm延長(MIRAI比) ・後席の居住空間を拡大 ・高い走行安定性 ・高級セダンとしての快適性 |
| CEV補助金 | 最大255万円 |
こんな方におすすめです。
- 法人の役員車・社用車として導入を検討している企業
- 後席の快適性を重視するショーファーカー用途
- 環境配慮と高級感を両立させたい方
トヨタ MIRAI(ミライ)

トヨタ MIRAIは、日本を代表する量産型燃料電池自動車です。2014年に初代が世界初の量産型FCVとして発売され、2020年に2代目へフルモデルチェンジ。洗練されたデザインと高い環境性能が特徴です。
2024年12月には初代モデル発売から10周年を記念して一部改良が実施され、「ブラック パッケージ」が新設定されました。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| メーカー希望小売価格 | 約741万円〜861万円 |
| 航続距離 | 約850km(WLTCモード) |
| 水素充填時間 | 約3分 |
| グレード | G、Z、Z Advanced Drive |
| 特徴 | ・クーペライクな流麗なデザイン ・FR(後輪駆動)レイアウト ・優れた操縦安定性 ・外部給電機能あり(AC100V/DC) |
| CEV補助金 | 最大255万円 |
こんな方におすすめです。
- FCVを個人で購入したい方
- デザイン性と環境性能を両立したい方
- 外部給電機能を活用したい方(災害時の電源確保)
- 長距離走行が多い方
ヒュンダイ ネッソ(NEXO)

ヒュンダイ ネッソは、韓国ヒュンダイが開発したSUVタイプのFCVです。グローバル市場では高い評価を得ており、ヒュンダイは後継車「イニシウム(Initium)」の2025年発売も予告しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| メーカー希望小売価格 | 約776万円 |
| ボディタイプ | SUV |
| 航続距離 | 約820km(NEDCモード) |
| 特徴 | ・SUVならではの高い実用性 ・広い室内空間 ・先進的なデザイン ・空気清浄機能搭載 |
| 国内販売状況 | リース販売中心(販売店要確認) |
こんな方におすすめです。
- SUVタイプのFCVをお探しの方
- 広い室内空間を重視する方(ファミリー向け)
- 海外メーカーの先進技術を体験したい方
ホンダ CR-V e:FCEV

ホンダ CR-V e:FCEVは、2024年7月に発売された最新モデルで、2024-2025日本カー・オブ・ザ・イヤーのテクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤー部門を受賞しています。
最大の特徴は、FCVでありながら外部充電も可能なプラグイン機能を搭載している点です。水素ステーションがない地域でも、EV充電設備で補給できる柔軟性があります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| メーカー希望小売価格 | 約809万円 |
| ボディタイプ | SUV |
| システム | 燃料電池+プラグイン充電可能 |
| 航続距離(参考値) | 約750km |
| 特徴 | ・外部充電可能なFCV ・SUVの高い実用性 ・最新技術搭載 ・テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤー受賞 |
| 販売形態 | リース専用(取扱販売店要確認) |
| CEV補助金 | 対象(リース利用者が申請) |
こんな方におすすめです。
- SUVタイプのFCVをお探しの方
- 水素ステーションが少ない地域にお住まいの方(充電でも対応可能)
- 最新技術を体験したい方
- リース契約で導入を検討している方
水素自動車は現時点では高額だが、今後に期待が持てるエコカー

水素自動車は、環境性能や走行性能の面で優れた特性を持っています。走行時に排出するのは水のみで、航続距離は約650〜850km、充填時間は約3〜5分という実用的なメリットがあります。
一方で、以下の課題も存在します。
- 水素ステーション:全国約149箇所(2030年までに1,000箇所目標)
- 燃料費:約11〜15円/km(2030年に大幅削減目標)
- 車体価格:約700〜1,000万円(補助金活用で500万円前後に)
政府は2025年までにFCV普及台数20万台、2030年代までに80万台を目指しており、インフラ整備と技術革新が進めば、水素自動車はさらに身近な選択肢となる可能性があります。
購入を検討する際は、自宅周辺の水素ステーション状況と、長期的なランニングコストを慎重に確認してください。特に以下の点をチェックしましょう。
- 自宅・職場から水素ステーションまでの距離と営業時間
- 国と自治体の補助金制度(併用可能な場合が多い)
- 4年間の保有義務期間を満たせるか
環境に配慮した選択をしたい方、最新技術に関心がある方にとって、水素自動車は今後に期待が持てるエコカーです。現時点での課題を理解した上で、長期的な視点から検討してみてはいかがでしょうか。
関連コラム

EV
【完全解説】カーボンニュートラル燃料とは?基礎知識からメリット・デメリットまで徹底解説

EV
自動運転機能付き軽自動車のおすすめは?現状と共に解説

EV
軽の電気自動車(EV)の充電方法は?設備費用やコストを抑えるコツも解説

EV
【2026年以降】電気自動車(EV)の今後はどうなる?メーカーごとの動きや購入前に知るべきポイントも解説

EV
プラグインハイブリッド(PHEV)とは?HV/EVとの違いを一覧比較!「充電しないとダメ?」の疑問からメリット・デメリット、おすすめ車種まで徹底解説

EV







