【2026年最新】自動車の自動運転が普及すれば道路の渋滞はなくなるのか?緩和・悪化の双方の根拠を徹底解説
更新日: 2026/2/21投稿日: 2025/7/2
EV
「自動車の自動運転が普及すると道路の渋滞はなくなる?」「車を気軽に利用する人が増えるから、逆に道路の渋滞が悪化する?」このような疑問をお持ちではありませんか?
自動運転には道路の渋滞を緩和させる要素も、悪化させる要素もあり、どちらの要素の影響がより大きいのかは、はっきりとはわかっていません。
本記事では、渋滞が緩和するとされる根拠と悪化するとされる根拠の双方を解説します。ぜひ最後までご覧ください。
そもそも自動運転とは?レベル3以上なら車に運転を任せられる

自動車の自動運転とは、人間のドライバーが行っている自動車の運転操作を、人間の代わりにシステムが行うものです。
自動車の自動運転には、レベル0~5までの段階があり、数字が大きいほど、システムによる運転操作への介入が大きくなります。
自動運転レベルはアメリカの非営利団体「SAE International(自動車技術者協会)」によって定められており、その内容は以下のとおりです。
| レベル | 概要 |
|---|---|
| 0 | 一切の自動化が行われていない状態 |
| 1 | アクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかが、部分的に自動化された状態。 |
| 2 | アクセル・ブレーキ操作およびハンドル操作の両方が、部分的に自動化された状態。 |
| 3 | 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。 ※ただし、自動運行装置の作動中、自動運行装置が正常に作動しないおそれがある場合においては、運転操作を促す警報が発せられるので、適切に応答しなければならない。 |
| 4 | 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。 |
| 5 | 自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。 |
レベル2以下の自動運転は、あくまで運転を行うのは人間で、システムはドライバーの運転操作を「支援」するにとどまります。
例えば、高速道路や自動車専用道路において、前方の自動車に追従して走行するといった機能が、レベル2に相当します。現在の日本で市販されている乗用車に搭載されている機能は、レベル2までです。システムに運転を任せて、人間が前方から目を離してもよいのは、レベル3以上の自動運転機能です。
本記事ではレベル3以上の自動運転が普及している社会を前提として、道路の渋滞が緩和するのか、それとも悪化するのかを検討しています。
自動運転でも適切な制御を行えば渋滞は緩和する方向へ

将来自動運転が普及したら、道路の渋滞は緩和するという意見が優勢です。少なくとも自動運転の自動車は、急な減速を行ったり、前方の自動車との車間距離を適切に保たなかったりすることによって、渋滞を引き起こすことはないと考えられるからです。
一方で、自動運転が普及すると、自動車を気軽に利用する人が増えるので、渋滞が悪化するといった意見もあります。しかし、自動運転が普及した社会では、自動運転車が車同士で通信したり、車と地上の間で通信したりすることが前提になっていると予想できます。
そのため、情報交換を通じて、全体の交通の流れを適切に管理すれば、渋滞は緩和に向かっていくと推察できるのです。
渋滞が緩和されると、自動車が加速・減速を行う機会が減少します。無駄なエネルギー消費が抑えられるので、環境への負荷も低減されます。
自動運転で渋滞は緩和する?悪化する?それぞれの意見を紹介

【緩和説】自動運転はなぜ渋滞を”減らせる”のか?4つの科学的根拠
1.渋滞発生を自動的に回避するので渋滞が減少する
自動運転車は、渋滞が発生しやすい道路、渋滞している道路を自動的に回避するので、渋滞は緩和すると考えられます。
自動運転が高度に普及している社会では、自動運転車がリアルタイムに道路交通情報を取得できることが前提になっているという考えが主流です。取得した情報に基づき、渋滞を回避するようにルート選択を行うので、渋滞は減少する可能性は高いといえます。
2.情報交換によって渋滞が発生する機会を減らせる
自動運転車は、他の自動車等と通信を行うことで渋滞の発生を回避できます。
人間のドライバーが自動車を運転している現在の社会では、無理な割込みや車間距離が短すぎることなどによって渋滞が起きています。極端なケースでは、約40kmもの渋滞が起きた原因が、たった1台の自動車の車線変更ということもありました。
しかし、自動運転が普及した社会であれば、自動運転車同士の通信や、自動車と地上の間での通信を行うようになっていると考えられています。そして、他の自動車の通行の妨げになりにくい速度制御や車間距離の保持が行えます。割込みや車間距離不保持に起因する渋滞発生を抑制できるのです。
3.人間のドライバーが無意識のうちに引き起こす渋滞が減少する
自動運転車は、人間のドライバーが無意識のうちに引き起こす渋滞を回避可能です。
高速道路では、サグ部(下り坂から上り坂に変わるような場所)やトンネルの入口で渋滞が起きやすいというデータがあります。また、トンネルの入口は、周囲が暗くなることによって、ドライバーがつい速度を落としてしまうことがわかっています。
速度が落ちると、スピードの低下が順番に後方へ伝わっていき、渋滞発生に至ってしまうのです。しかし、自動運転車であれば、サグ部やトンネルの入口に差し掛かっても速度を保てるので、渋滞緩和の効果が期待できます。
また、高度な自動運転車ではない、運転支援装置であるACC(定速走行・車間距離制御装置)を搭載した自動車であっても、サグ部等での渋滞の緩和には有効です。なお、ACCを使用して走行している自動車が10%程度存在するだけでも、渋滞緩和の効果があるとされています。
このことから、自動運転レベルの高い自動車だと、より渋滞が緩和されるでしょう。
参照:オートパイロットシステムの実現に向けて 中間とりまとめ 参考資料集 国土交通省
4.交通事故の減少に伴って渋滞が減少する
自動運転が普及すると、交通事故の発生件数が大幅に減り、事故に伴う渋滞も減ると考えられます。交通事故はひとたび発生すると、車線規制や通行止め、周囲を通行する車の速度低下といった渋滞の原因を引き起こします。
自動運転車は人間が運転する自動車と異なり、不注意や居眠り、交通違反などによって事故を起こすことはありません。したがって、交通事故は大幅に減少するでしょう。車線規制、通行止めなどに起因する渋滞が発生する機会も減ると予想されます。
【悪化説】楽観できない?自動運転が渋滞を”増やす”3つのシナリオ
1.自分で運転しないのなら渋滞していても構わない人が増える
自動運転の普及によって、渋滞する道路を通っても構わないという人が増えるかもしれません。
人間が自動車を運転する場合、渋滞中の道路での運転は、ドライバーに一定の負担を強いるものです。頻繁に加速・停止を繰り返さなければならないし、前方の自動車に追突しないよう常に注意を払わなければなりません。
しかし、自動運転車であれば、渋滞している道路を通るときも、乗員は運転せずに読書などをして待っていればよいだけです。先を急いでいないならば、道路が渋滞していても構わないという人が、一定数出てくると考えられます。自動車が特定の道路に集中して、渋滞が悪化してしまうかもしれません。
自動車が特定の道路に集中することを回避するためには、自動車それぞれが思い思いのルートを選択するのではなく、広範囲の道路へ交通量が分散するようにルート選択を行う必要があります。
2.自動車を利用する人が増えるので渋滞が悪化する
自動運転が普及すると、自動車を利用する人が増えるため、渋滞が悪化する可能性があります。自分で自動車を運転できない人が、自動車で自由かつ安全に移動できるようになることは、ひとつのメリットです。しかし、自動車で移動する人が増えると、道路の交通量が増え、渋滞が悪化する可能性があります。
また、自動運転の普及によって、ライドシェアやカーシェアといったサービスが充実していくでしょう。サービスが充実して、鉄道やバスといった公共交通機関を利用するよりも廉価な移動手段になってしまうと、さらに渋滞が悪化するのではないかということも懸念事項です。
3.自動運転車と人間が運転する自動車が混在していると渋滞が悪化する
自動運転が普及し始めたタイミングにおいては、自動運転車と人間が運転する自動車が混在する状況になり、一時的に渋滞が悪化する可能性があります。
自動運転車は、定められた制限速度を順守して走行すると考えられます。また、車間距離を人間が運転する自動車よりも長めに確保するでしょう。自動運転車と人間が運転する車の連携がうまく取れず、車の列が間延びしてしまうかもしれません。
また、自動運転車のシステムが、人間のドライバーの操縦意図を理解できなかったり、人間が運転する自動車が自動運転車の前に無理な割込みを行ったりすることもあるでしょう。時間が解決する問題ではありますが、最初は特に渋滞の原因が増える可能性があります。
渋滞対応支援機能のついている自動車のメーカー5社を紹介

レベル3以上の自動運転機能が搭載された乗用車は日本国内では現在市販されていません。レベル3以上の自動運転が一般的になる社会の到来までには、まだ時間がかかると考えられます。
しかし、レベル2の運転支援機能にあたる、高速道路や自動車専用道路向けのACC(定速走行・車間距離制御装置)であっても、ある程度の渋滞緩和には役立つとされているのが現状です。また、ACCの中には高速域での定速走行や、先行車への追従走行機能を備えているのみならず、渋滞中の低速走行時にも、先行車に追従して走行する機能を備えているものがあります。
ここでは、渋滞にも対応した運転支援機能をリリースしている自動車メーカーを紹介しますので、参考にしてください。なお、ここで紹介する運転支援機能は、必ず高速道路や自動車専用道路で使用してください。また、自動運転装置ではありません。ドライバーには手動運転の場合と同様に、安全に運転を行う義務があります。
1.日産:プロパイロット
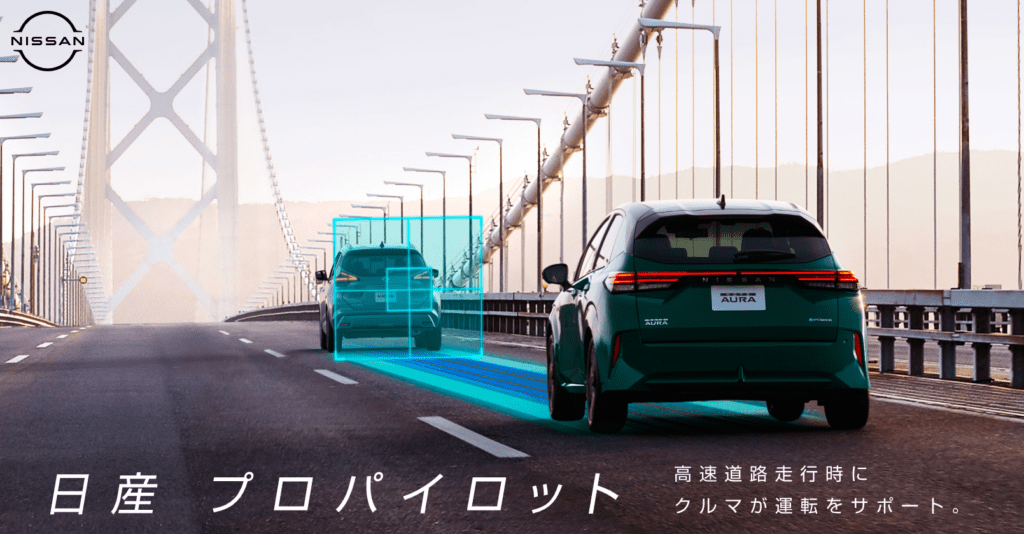
日産の「プロパイロット」は、高速道路の運転時に、アクセル・ブレーキ・ステアリング操作をアシストする機能です。
先行車が停車している場合は、システムが自動的にブレーキをかけて停車し、ブレーキペダルを踏まなくても停止状態が保持されます。先行車が発進した時に追従走行を再開するための操作は、スイッチを押すかアクセルペダルを軽く踏むだけです。
「プロパイロット2.0」は、さらに高度な機能を備えており、ナビゲーションシステムに連動したルート走行機能や、他車を追い越す操作のアシストを行う機能があります。
対応車種は以下の通りです。
| 機能 | 対応車種 |
| プロパイロット | 日産アリア 日産リーフ 日産サクラ ノート オーラ ノート エクストレイル キックス セレナ ルークス デイズ |
| プロパイロット2.0 | 日産アリア セレナ |
2.ホンダ:渋滞追従機能付きアダプティブクルーズコントロール/トラフィックジャムアシスト
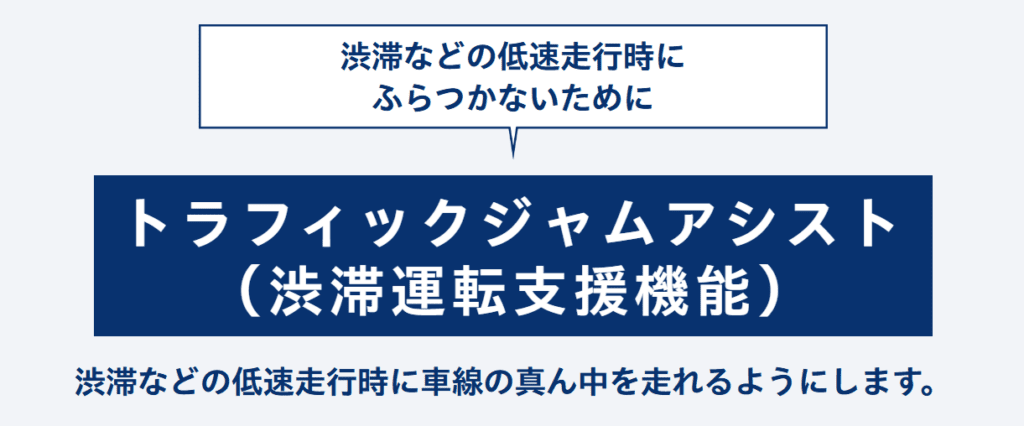
ホンダの「渋滞追従機能付きアダプティブクルーズコントロール(ACC)」は、先行車が停止したら自車も自動的に停止する機能を備えています。先行車が発進したら、スイッチ操作またはアクセルを踏むことで、追従走行を再開。
「トラフィックジャムアシスト」は、渋滞などの低速走行中に、車線の中央付近を走れるように、ステアリング操作の支援を行う機能です。両方の機能を備えている車種は、以下のとおりです。
- フィット
- ステップワゴン
- フリード
- ヴェゼル
- ZR-V
- CR-V e:FCEV
- シビック e:HEV
- シビック CVT
3.トヨタ:アドバンスト ドライブ
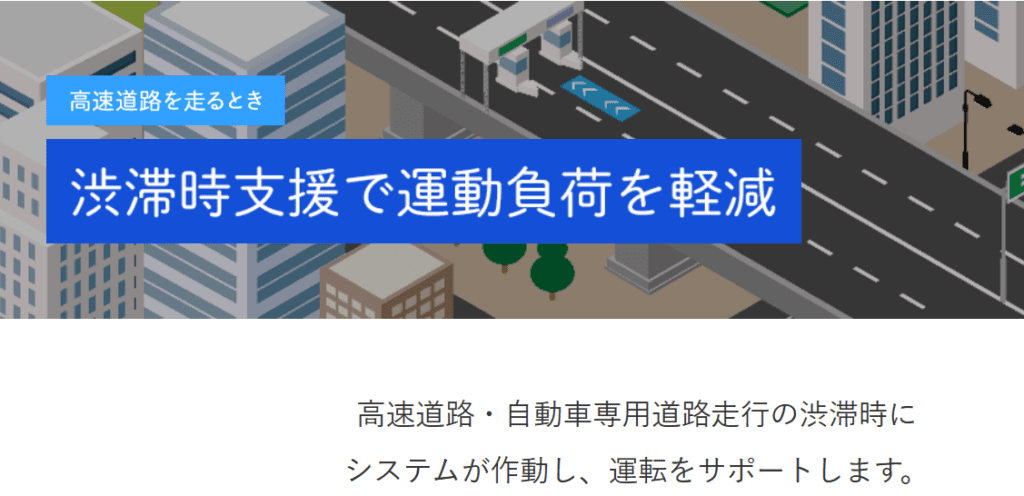
トヨタの「アドバンスト ドライブ」は、時速約40km以下の低速走行中に、ハンドル操作や加減速、停止を自動的に行います。ドライバーが前を向いているなどの一定の条件を満たしていないとシステムが動作しないので、脇見運転などを誘発しないようになっています。
また、特定の高速道路等でなければ動作しないので、一般道での不適切な使用ができないことも特徴です。搭載車種は以下のとおりです。
- アルファード
- ヴェルファイア
- ヴォクシー
- ノア
- クラウン
- クラウン(エステート)
- クラウン(クロスオーバー)
- クラウン(スポーツ)
- MIRAI
- ランドクルーザー”250″
- センチュリー
4.スバル:アイサイトX
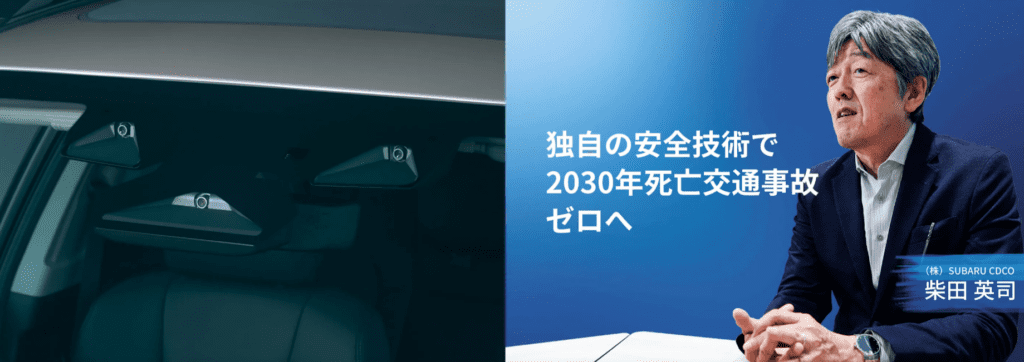
スバルの運転支援機能である「アイサイトX」には、渋滞時(走行速度が時速0~50kmのとき)に一定の条件を満たすと、ハンドルから手を離すことが可能になる(ハンズオフ)機能が備えられています。
先行車との間に割り込む自動車があっても、自動的に減速されます。搭載車種は以下のとおりです。
- フォレスター
- レイバック
- クロストレック
- レガシィ アウトバック
- レヴォーグ
- WRX S4
5.BMW:ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能

BMWの「ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能」は、高速道路を時速60km以下で走行中といった条件を満たすときに、自動でハンドル操作、アクセル操作、ブレーキ操作を行う機能。名前通り、ハンドルから手を離すことも可能です。
BMWは海外のメーカーではありますが、渋滞時のハンズ・オフ走行を日本で初めて可能にしたことが特徴です。2019年7月以降に発売されたBMW3シリーズ以降のモデルでは、ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能が標準装備となっています。
【まとめ】高度な自動運転が普及すれば道路の渋滞は緩和していく

自動運転は、道路の渋滞を緩和させる要因と、悪化させる要因を併せ持っています。しかし、高度な自動運転が普及した社会では、自動運転車が道路の交通の流れを良くするための運転操作やルート選択を行えば、道路の渋滞は緩和していく方向に進んでいくと考えられます。
今後も当メディアでは、自動運転やEVなどのモビリティなどに関するニュースをまとめて発信していきます。最新情報が気になる場合は、ぜひ定期的にチェックしてみてください。
関連コラム

EV
【2026年最新】中国の電気自動車(EV)が注目される理由は?日本で買える車種や注意点を解説

EV
【総まとめ】電気自動車(EV)のメリット7選!デメリットをカバーする方法も合わせて解説

EV
EVとガソリン車を徹底比較!購入費・走行性能・将来性能など6つの違いを解説

EV
【完全解説】カーボンニュートラル燃料とは?基礎知識からメリット・デメリットまで徹底解説

EV
電気自動車(EV)のデメリット7選と3つの誤解。「買ってはいけない」は本当?購入後に後悔しない全知識と解決策

EV









