自動運転とAIはどういう関係?現状と課題を解説
更新日: 2025/11/13投稿日: 2025/5/26
EV
「自動車の自動運転って、どの程度実現しているんだろう?」
「自動運転ってどういう仕組みで行うんだろう? AI(人工知能)を使うのかな?」
「自動運転の技術って、どこの企業が開発しているんだろう?」
こんな疑問をお持ちではありませんか?
近年はAIの技術が大きく進歩していることは、皆さんもご存知の通りです。そして、自動車の自動運転にも、AIの技術が深く関わっています。そこで、今回の記事では以下の内容を解説します。
- 自動運転とAIの関わり
- AIによる自動運転が抱えている課題
- 自動運転に関連する技術開発を行っている企業
自動運転とAIに関連する技術について知りたい方や、開発を行っている企業(自動運転に関連する銘柄)を知りたいといった方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。
自動車の自動運転の現状とは?レベル0~5の5段階に分類される

自動運転とは、車両がシステムやAI(人工知能)を利用してドライバーの運転を支援する、あるいはドライバーの代わりに運転を行う技術です。
自動車の自動運転には、レベル0~5までの段階があり、数字が大きいほど、システムによる運転操作への介入が大きくなります。自動運転レベルはアメリカの非営利団体「SAE International(自動車技術者協会)」によって定められており、その内容は以下のとおりです。
| レベル | 概要 |
|---|---|
| 0 | 一切の自動化が行われていない状態 |
| 1 | アクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかが、部分的に自動化された状態。 |
| 2 | アクセル・ブレーキ操作およびハンドル操作の両方が、部分的に自動化された状態。 |
| 3 | 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。 ※ただし、自動運行装置の作動中、自動運行装置が正常に作動しないおそれがある場合においては、運転操作を促す警報が発せられるので、適切に応答しなければならない。 |
| 4 | 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。 |
| 5 | 自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。 |
レベル2以下の自動運転は、あくまで運転を行うのは人間で、システムはドライバーの運転操作を「支援」するにとどまります。そのため、レベル2以下の自動運転機能を備えている自動車は、厳密に言えば「運転支援車」であり、自動運転車とは言えません。自動車メーカーも「自動運転ではありません」と明示しています。
レベル2の機能を搭載した自動車は実用化・市販化されており、誰でも購入が可能です。
レベル3以上の自動運転では、特定の条件下で自動運行装置が人間に代わって、全ての運転操作を行います。そのため、ドライバーは前方から目を離せます(アイズオフ)。
レベル3の自動運転車は、ホンダのLEGEND(レジェンド)によって世界で初めて実現しましたが、生産台数が限定されており、既に市販されていません。海外でも実例は少ないです。
レベル4の自動運転車は、限定的な環境での導入にとどまっています。
2023年5月に、福井県永平寺町で日本初の、レベル4の自動運転による移動サービスが開始されました。ただし、鉄道の廃線跡地に敷かれた道路を利用して、運行速度は時速12km以下という、極めて限定的な条件下での自動運転です。
また、2024年12月には愛媛県の松山市で、路線バスとしては日本初の、レベル4の自動運転による営業運転が始まりました。この事例も、運行ルートが決まっている路線バスだから実現できたという背景があります。
電車・バス情報 | IYOTETSU EV AUTONOMOUS 全国初「自動運転レベル4」完全自動運転 路線バス | 伊予鉄
一般的な乗用車によるレベル4の自動運転は、まだまだ実用化していないのが現状です。
日本の自動運転の進捗については、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひご確認ください。
自動車でAI技術が活用されている5つの場所

自動運転の技術を発達させるためには、AI関連技術が欠かせません。そして、AI技術が活用される場所は、加速・減速やステアリング操作といった、運転操作の自動化に関わる部分だけではないのです。
こちらでは、AI技術が活用されている場所について解説します。
1.自動運転における認知・判断・操作
自動車が自動運転を行うためには、「自動車の周りに何があるのか」といった情報を、カメラやレーダーなどを用いて収集する必要があります。AIは画像認識によって、何が映っているのか判断します。
また、何が映っているのかを理解した上で、安全上の問題はないとするのか、減速するのか、ステアリングを切って回避するのか、といった判断や操作を行うのもAIの役割です。
2.ルート判断
自動運転車には、出発地から目的地までの最適なルートを判断する能力が求められます。そこで、中継地点や目的地の場所、経路の渋滞予測や工事の情報に基づいて、最適なルートを選択するAIが必要です。
将来的には、配送業者の自動車が「どのようなルートで回るのが効率的なのか」を、AIが判断するようにもなるでしょう。
3.音声アシスタント
自動運転車では、乗員の意図をシステムが理解して、目的地や走行ルートを決定する材料とする必要があります。乗員と自動車のコミュニケーション方法の形態として考えられるのが音声アシスタントです。
音声アシスタントは、乗員の発する言葉を正確にとらえて、乗員の要求を理解し、自動車の運転に反映する必要があります。
また、乗員同士の(自動車にとっては意味のない)会話と、自動車への指示を区別するといった機能も求められます。このような機能もAIによって実現可能です。
4.ネットセキュリティ向上
自動運転車は、様々な情報を取得するために、ネットワークへの接続が常時行われると考えられます。そのため、サイバー攻撃を受ければ、自動車の制御が行えなくなり、事故につながる危険性があるのが課題です。
サイバー対策としてセキュリティの向上が必要となりますが、この分野でもAIが活用されています。例えば、正常なプログラムと脅威となるプログラムの判別や、どのような脅威が想定されてどのように対策するかといったシミュレーションなどに、AIが活用可能です。
5.その他
タクシーの需要を予測して、自動運転タクシーの配車を効率的に行ったり、自動車販売業者の試乗案内をAIに行わせたりするといった、サービスを豊かにする方向でも、AIの活用方法が検討されています。
AIを活用した自動運転の4つのメリット

AIを活用して自動車の自動運転技術が発達すると、社会にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは4つのメリットを紹介します。
1.安全性の向上
人間が運転する自動車は、ドライバーが疲れたり注意が散漫になったりすることで、運転操作を誤り交通事故を起こすことがあります。しかし、疲れや注意力の低下は人間ならではのものであり、AIでは起こりません。
また、AIは危険を認知してから応答するまでの速度や、適切な応答方法を選択する能力においても、人間よりもはるかに優れていることが期待されます。
以上の理由で、交通事故は大幅に減少して安全性が向上することでしょう。
交通渋滞の減少
自動運転を行うシステムは、ネットワークに接続していることが前提なので、自動運転車同士での情報共有が行えます。共有した情報をもとに、交通の流れをリアルタイムに分析することによって、特定の道路に交通が集中する状況を回避できます。
環境に対する負荷の減少
自動車の加速・減速の頻度を減らしてエネルギー効率を向上させたり、渋滞の発生を回避したりできます。
その結果、ガソリンの使用量が減る、渋滞中の排気ガスが減るなど、環境に対する負荷が減少することが期待されます。
移動手段の革新
人間が自動車を運転する必要がなくなるため、自分で運転できない人を含めた多くの人々が、自動車で自由に、安全に移動できるようになります。
また、無人の状態でも自動車の回送が行えるので、カーシェアリングやライドシェアリングが効率化されて、爆発的に普及する可能性があります。自動運転の実用化は、バスやタクシーのドライバー不足の問題を解決すると期待されていますが、そもそもバスやタクシーのあり方自体が大きく変わるかもません。
目的地に着いた後で自動車を、無人状態で駐車場まで走らせることもできます。したがって、地価が高い都心部に、わざわざ多くの駐車場を備える必要がなくなります。駐車場だった土地を商業施設や公園に変えるといった、土地活用方法の変革にもつながることでしょう。
AIを活用した自動運転の課題とは

AIを活用した自動運転技術は年々進歩してはいますが、実用化・普及させるためには、様々な課題が待ち受けています。
不完全知覚問題
自動運転における不完全知覚問題(ふかんぜんちかくもんだい)とは、自動車に搭載されたセンサーから得られる情報量には限界があり、あらゆる状況を判別することは不可能なのではないかという懸念です。
過去には、AIが誤ってトレーラーの荷台部分を交通標識だと認識したために、トレーラーの荷台の下を通過しようとして追突事故に至ったケースがあります。このような、人間ならばまず行わないような誤った判断をAIが下してしまう可能性を、ゼロにすることは現状難しいと考えられています。
切り替え問題
レベル3の自動運転においては、AIが危険を予想して、AIでは対処しきれないと判断した場合に、人間のドライバーによる手動運転に切り替わります。
しかし、急な運転操作の引継ぎに、人間が対応しきれなかったことが原因で事故が起きています。これでは、AIが運転を続けた方がまだよい結果になった可能性があります。なぜ危険なのか、人間のドライバーにどうしてほしいのかを、どうやってドライバーに伝えるのかが課題です。
この切り替え問題が存在することから、レベル3よりもレベル4を導入する方が現実的ではないかという意見さえもあります。
データ量が多すぎる問題
AIによる自動運転では、システムが多くの情報を処理したり、ネットワークを通じて送受信したりします。中には、自動車に搭載されたハードだけで処理するには重いタスクも想定されます。
そこで、クラウドにデータを送信し、処理はクラウド側で行って、処理結果を自動車が受信するという方式が検討されています。しかし、この場合も、クラウドでデータを送受するために莫大な通信量が発生するという問題や、一連の処理にかかる時間(遅延)の問題があります。
倫理的問題(トロッコ問題)
「トロッコ問題」とは「ある人を助けるために他の人を犠牲にするのは許されるのか」などといった倫理的な問題です。
自動車の自動運転の場合は「乗員と車外の通行人のどちらかの負傷が避けられない事態になった場合に、どちらを助けることを優先するのか」といった問題が考えられます。このような事態への対処方法をシステムの設計に反映しなければならないので、避けては通れない問題です。
この問題への対処の判断基準としては、例えば下記の4通りが考えられます。そして、そのいずれも、これが絶対に正しいとはいえないはずです。
- 負傷するのが外部の人間か乗員かで判断する?
- 負傷する人が多いか少ないかで判断する?
- 負傷しうる人の属性(年齢など)で判断する?
- 急ブレーキをかけるといった、事故回避・被害低減のための最大限の努力を行うことを重視して、結果は問題としない?
トロッコ問題をはじめとした倫理的問題に、決定的な解決策はないとしても、ドイツで可決された「自動運転法」は、一定の指針を出しています。この法律では「人命へのリスクが避けられない場合は、個人的な特徴(年齢・性別など)をもとに、人命の重み付けを行わない事故防止システムを備えること」と定められています。
ただし、この指針に対しても、例えば「子どもの命は優先的に守るべきだ」といった批判は存在し、それもまた一定の正論と言えるでしょう。
法的問題
現在の道路交通法といった交通法規は、人間が運転する前提で作られているので、自動運転車に対応した法律や規制の整備が必要です。
例えば、自動車運転処罰法の第五条には「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」と書かれていて、明らかに人間のドライバーを想定した条文となっています。自動運転車の存在を前提とした法整備が必要です。(参考:衆議院ホームページ)
また「自動車の運転上必要な注意」とは具体的に何なのかがそもそも明文化されていません。そのような抽象的な概念を、どのようにAIに実装できるのかも、課題となるでしょう。
他にも、自動運転車は様々な情報の収集を行いますが、個人情報をどこまで保護するか、どうやって保護するかといった課題もあります。
事故が起きた時の責任の問題
法的問題とも関連しますが、レベル3以上の自動運転車が万が一事故を起こした場合に、誰が責任を負わなければならないのかも、議論の対象となっています。
自動運転車の事故は、自動車の製造者が責任を負うことになるという意見が主流ではあります。しかし、製造者が責任を負わなければならないならば、自動運転が自動車の製造者にとって「割に合わないもの」と判断されて、技術開発の妨げになる懸念も指摘されています。
AIによる自動運転の関連技術を開発している企業(自動運転関連銘柄)
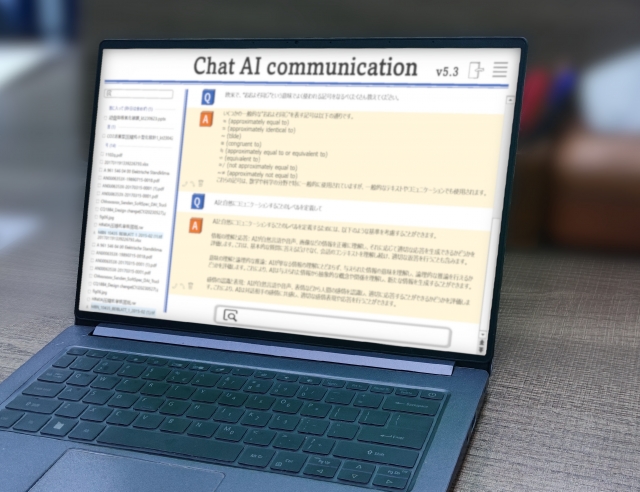
自動運転の技術には、センサーや通信、AIによる自動運転システムなどの様々な要素が関係しています。そのため、自動運転の開発に関わっている企業(自動運転関連銘柄)も、多岐にわたります。ここでは日本国内の自動運転開発に関わっている企業の一部を紹介します。
※下記銘柄一覧はあくまで「自動運転関連銘柄である」ことを示すものです。銘柄の売買を推奨するものではありません。
自動運転車開発
- トヨタ自動車(7203)
- ホンダ(7267)
- 日産自動車(7201)
自動運転システム開発
- ソリトンシステムズ(3040)
- マクニカホールディングス(3132)
センサー開発
- ソニーグループ(6758)
- オムロン(6645)
- IDEC(6652)
- 京セラ(6971)
アンテナ開発
- シャープ(6753)
通信関連
- 住友電気工業(5802)
- 日本電信電話(NTT)(9432)
- KDDI(9433)
- ソフトバンク(9434)
3次元マップ
- アイサンテクノロジー(4667)
- ビーマップ(4316)
- ゼンリン(9474)
【まとめ】完全自動運転の実現にAIの技術の進歩は必須!

自動運転車においては、運転操作そのものに加えて、ルート決定、乗員へのアシスタントなどの様々な分野で、AI技術が使われています。
そして今やAIは、自動的に判断力を向上させることや、新たなコンテンツを生み出すことも可能となり、その能力を日々向上させています。レベル4やレベル5の完全な自動運転の普及も、それほど遠い未来のことではないのかもしれません。
今後も当メディアでは、自動運転やEVなどのモビリティなどに関するニュースをまとめて発信していきます。最新情報が気になる場合は、ぜひ定期的にチェックしてみてください。
関連コラム

EV
プラグインハイブリッド(PHEV)とは?HV/EVとの違いを一覧比較!「充電しないとダメ?」の疑問からメリット・デメリット、おすすめ車種まで徹底解説

EV
電気自動車(EV)の充電時間の目安は?充電の種類や時間短縮の方法も解説

EV
【総まとめ】電気自動車(EV)のメリット7選!デメリットをカバーする方法も合わせて解説

EV
【2025年版】EVバスとは?日本国内の導入事例や主要メーカーまで徹底網羅

EV
電気自動車の走行距離はどれくらい?車種別の目安やガソリン車との比較を紹介

EV









